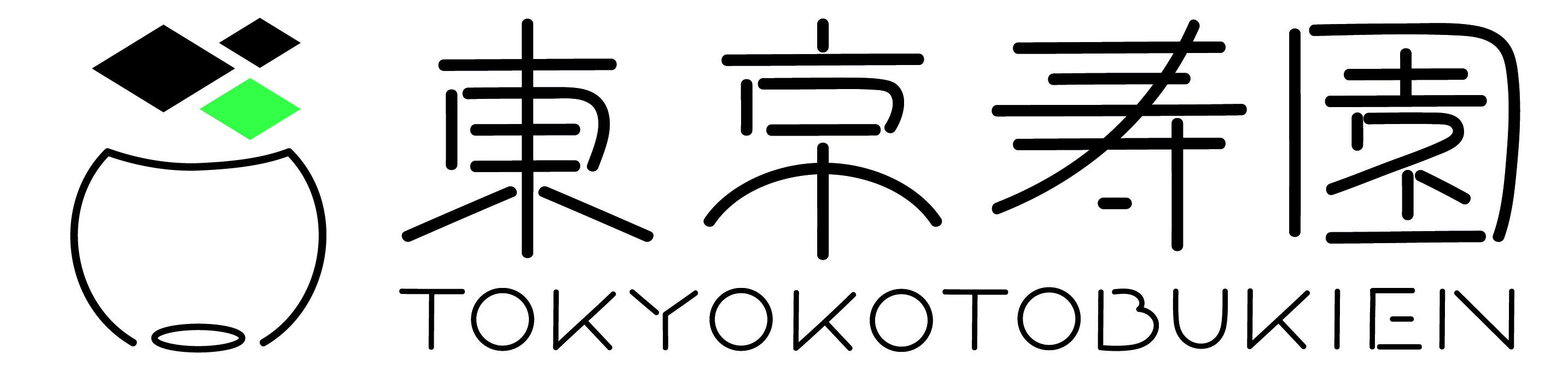目次
見た目の可愛さや初めての方でも簡単で育てやすい理由から人気の観葉植物「パキラ」。水やりや温度管理などを懸命に行っているとき、気づいたら土が綿状の白いもので覆われていたらどうしますか。せっかく育てているのにとショックを受ける方も多いでしょう。
しかし、パキラを育てる環境や温度管理が間違っていることによりパキラの土が白くなる状況にしている方も少なくありません。
「この白い正体は何?」「どうやって対処したらいいの?」と、原因も分からず、どう対処していいのか悩んでしまう方もいるのではないでしょうか。
この記事では以下の点についてまとめていきます。
- 土についた白いものの正体とは
- 土が白く覆われる原因とは
- 人体に影響はあるのか
- 白く覆われた土やパキラの対処法とは
- パキラが病気になる可能性は
パキラの土が白くなるのはどうして?
パキラの土が白くなっていたら驚く方も多いでしょう。「白いものの正体は何?」「どうして土が白くなるの?」と、悩む方も少なくありません。 土が白くなる原因はパキラの育てる環境が関係してきます。 下記ではパキラの土が白くなる理由やパキラに影響がないかについて詳しくお伝えします。カビが生えて白くなるから
土の表面が白くなる原因はカビが生えているからです。パキラは寒さや乾燥に強く丈夫な観葉植物ですが、湿気が高い状態や水やりの管理ができていない理由からパキラの幹や土に白いカビが生えやすくなります。その結果、パキラが病気になったり、枯れてしまったりする可能性がみられます。また、土の表面に撒いた有機肥料にも白カビは生えます。しかし、この白いカビはウイルスや病気の元となる菌の繁殖はせず、酵母菌によってできたカビのためパキラには影響はありません。カビが生えるとパキラが枯れてしまうことがある
土や肥料の表面に生えたカビをすぐにみつけて取り除く作業を行うことでパキラが枯れる可能性は低くなります。しかし、パキラの幹までカビが生えているときは枯れてしまう場合もあります。 なぜなら、パキラを育てる環境によって根腐れを引き起こしている可能性があるからです。土が湿った状態が続くと土の中の酸素が不足しパキラが窒息状態になることで根が腐れます。その結果、パキラの幹に白いカビが生えて枯れてしまいます。カビの胞子は人体にも悪影響がある
カビの胞子は目に見えないですが、空気中に漂っています。植物に生えるカビはごく僅かな量ですが、毎日吸い続けることでアレルギーの原因になるといわれています。 咳や鼻水などの症状が発症し、進行すると呼吸困難や肺炎になるリスクがありますので注意は必要です。カビで発生させない育て方やコツを紹介します
カビが生えないようにするにはカビを発生させない環境をつくることが重要です。カビは温度や湿気などの条件が揃うと一気は繁殖しますが、日当たりや通気性の良い場所を嫌いますのでカビの発生を抑制できます。 また、前もってカビ予防用の殺菌剤を使うことをおすすめします。ほかにも、重曹やシナモン、リンゴ酢といった天然の抗カビ剤を土に撒くことでカビの発生を防ぎます。天然の抗カビ剤は植物に影響がないので安心して使うことができます。パキラの土にカビが生えた時の対処法
土に生えた白いカビをそのまま放置するとパキラが病気にかかりやすくなり、また人体への影響が大きくなります。カビを見つけたときに、すぐ対処することでパキラの枯れや病気の予防にも繋がります。下記ではカビが生えた時の対処法を詳しくお伝えします。対処法①:土を入れ替える
白いカビが土の表面だけに生えている場合、表面だけの土を新しい土に入れ替えてください。ただし、白いカビが土の表面だけではなく鉢の底穴からも発生しやすいため、土に中までカビが生えている場合もあります。そのときは土をすべて入れ替えることが良いでしょう。カビが生えてしまった土はそのまま廃棄することもできますが、アルコールやお酢で消毒を行い天日干しをしよく乾燥させることで再利用できます。対処法②:エタノールやお酢で殺菌する
土に生えたカビはエタノールやお酢を吹きかけることで簡単に殺菌効果が期待できます。また、パキラを日当たりの良い場所に置くことで、殺菌効果が高くなるといわれています。エタノールやお酢を使い殺菌する場合、植物に吹きかけると葉っぱや幹などパキラの生長に影響がでる可能性がみられます。そのため、カビに吹きかけるときはパキラの葉っぱや幹にかけないように注意してください。パキラは直射日光を当てると葉焼けする恐れがありますので、日光が当たらないようにカーテン越しに置くのが好ましいです。対処法③:観葉植物専用のカビ取り剤を使う
カビが大量発生しアルコールやお酢では効果が見込めない場合、園芸店やホームセンターなどに売っている観葉植物専用のカビ取り剤を選び使いましょう。スプレータイプや化粧石タイプの防カビ取り剤があります。化粧石タイプはカビが発生する前に土が隠れる程度に敷き詰めることでカビ予防に繋がり、見た目もおしゃれになるのもおすすめです。パキラの土に白カビが生える原因は大きく3つ
パキラの土が白くなる原因がカビということをお伝えしました。では、どうしてカビが発生したのでしょうか?白いカビが発生する背景にはカビが好む環境があるといわれています。ここでは、白いカビが発生する原因について詳しくお伝えしていきます。原因①:日当たりや風通しが悪いところに置いてる
日当たりや風通しが悪い場所にパキラを置いていると白いカビができやすくなります。部屋の換気をしていてもパキラの置き場所によってカビの生えやすさに違いが出てきます。たとえば、窓際と部屋の中心とでは日当たりや風通しが全く違い、部屋の中心に置いているとカビが生えやすいです。また、パキラの土の表面に「マルチング」は置いてないでしょうか?マルチングとは観葉植物の土の表面をおしゃれに見せてくれるものです。「カラーストーン」や「ココヤシファイバー」といった種類があり、どれも100均やホームセンターなどで手軽に購入できます。マルチングも土の通気性を悪くする原因になりそのうえ、マルチング自体が水分を吸い上げるため白いカビの原因のひとつになります。また、植木鉢がプラスチック製の場合、通気性が悪く多湿状態になりやすいため白いカビが発生しやすくなります。原因②:過剰な水分で常時土が湿っている
パキラへの過剰な水やりは白いカビの原因に繋がります。パキラが十分に水を吸収していない状態で水を与えてしまうと、白いカビが好む環境になります。また、受け皿に溜まったままの水を放置している場合も多湿な環境を作っています。冬の時期はパキラの生育速度が落ちて吸水速度も落ちるので、水やりの量を調整しないと多湿状態が持続する状況下になってしまいます。
原因③:肥料を過剰に与えている
肥料のやりすぎは、パキラが栄養を吸収する量を超えてしまうと肥料がカビのエサになります。カビのエサ以外にも肥料のやりすぎは肥料焼けの原因にも繋がります。冬場はパキラが休眠期になり、ほとんど成長しないので肥料を与えなくても問題ありません。パキラの土に白カビを発生させない日頃のケア
普段、行っているパキラのケアが、もしかするとカビが発生しやすいようになっているかもしれません。日頃から行っている水やりやパキラの置き場所など見直してみませんか。水やり管理や置き場所を意識をすることで白いカビの発生を抑えることが可能になります。ぜひ、試してみてください。【日当たり】【風通し】が良好な場所に置く
前述したとおり日当たりや風通しは、窓際と部屋の中心では全く違います。白いカビは紫外線を嫌う習性もありますので、パキラは日当たりや風通しの良い窓際に置いてあげましょう。しかし、パキラは直射日光を当てると葉焼けする可能性もあり、直射日光を嫌うためカーテン越しで日光を当てましょう。 マルチングもオシャレではありますが風通しを良くするといった点では置かないほうがカビ予防にも繋がります。また、植木鉢もプラスチック製を使っているなら通気性の良い素焼き鉢へ変えるのもよいでしょう。水やりは土の表面が乾いてからたくさん与える
水やりのタイミングは、土が乾いている状態が確認できてから行うようにしましょう。土の表面が乾いてるように見えても土の中はまだ湿っているということがありますので、土の表面が白っぽい茶色になってからあげてください。ここでもマルチングは土の表面の乾きなどを確認しにくくなってしまいますのでおすすめはしません。 水やりでは土が乾いてる状態が確認したのち、たくさん与えてください。水をあげたつもりでも土の中の隅々まで行き届いていないということもあります。ただし、鉢の底に受け皿をしている場合は白いカビの好む多湿状態を作ってしまいますので注意してください。肥料は適切な量を与える
パキラに与える肥料は多すぎても少なすぎてもいけません。季節によって肥料を与える量に違いが出てきますので注意しましょう。春はパキラは生育が活発になっていくので、2ヶ月に1回ペース、夏は最も生育が活発になるので2週間に1~2回のペースで肥料を与えるのが好ましいです。なぜなら、気温が高くなるとパキラの土の微生物も活発になり、肥料の分解が早くなるからです。秋から冬にかけて気温が低くなり始めると、休眠期に入るため成長しなくなりますので肥料を与える必要はなくなります。白カビは土だけではなく葉にも悪影響を及ぼす
白いカビはパキラの土だけではなく、葉の表面にもカビは発生します。葉の表面に発生した白いカビはパキラに病気を発症することもあり危険です。土の表面に生えるカビとは違い、放置したままにするとカビが株全体に広がるだけでなく、周辺の植物にも影響を与える可能性があります。
うどんこ病を引き起こすことがある
うどんこ病とは、葉っぱの表面に白いカビが生えるとき、見た目がうどんの粉をまぶしたような模様になる病気です。うどんこ病の症状が進行するとパキラの葉っぱだけではなく全体が白になり、生長ができなくなったり、葉や茎が変形がみられます。 うどんこ病はウドンコカビが植物に付着することが要因となり、ウドンコカビが植物の栄養を吸い取り繁殖します。白い粉のようなようなものがあるときは要注意
パキラの葉っぱに白い粉のようなものを見つけたときは注意が必要です。 うどんこ病は土や落ち葉の中にいる糸状菌(しじょうきん)といわれるカビが原因で発症します。5~6月と9~11月の時期に発生しやすく、ほぼ全ての植物に発症する可能性があります。カビが繁殖して白くなった箇所は光合成を行えず、放っておくと葉が枯れて繁殖した菌が他の植物に移っていきます。 糸状菌は気温が高く乾燥した環境を好み、風に飛ばされることで他の植物に付着して増殖を繰り返します。うどんこ病には重曹がよく効きます
うどんこ病には重曹を使うことで効果があるといわれています。重曹1gに対して水500~1,000mlで薄めた重曹スプレーを作ります。アルカリ性の重曹スプレーをうどんこ病になっている部分に噴きかけることで原因となっている菌を死滅させることができます。 効果が薄いときは噴きかけた部分が乾いてから何度か噴きかけてみてください。ただし、重曹の濃度が高いとパキラが変形したり枯れたりすることもありますので注意が必要です。【豆知識】土が白いのはカビが原因じゃないときもある
ここまで読んでいただくと、パキラの土が白くなるのは白いカビが原因だと判断することでできます。しかし、土が白くなる原因はカビだではありません。 パキラの株本や土の表面に白い絹糸状なものが現れた場合、「白絹(しらきぬ)病」と呼ばれる病気の可能性が高いです。カビのように見えてしまう【白絹病】って知ってますか?
白絹病とは糸状菌など様々な病原菌から引き起こされる病気です。見た目は白や黄色の丸い粒の形や絹状になっているのが特徴です。発病気温は25℃以上なので5月~9月の暑い時期に発生しやすく、30℃を超えると菌が増殖します。周囲にある植物への感染力が強いため、注意が必要です。白絹病にかかったパキラは助からない
1度白絹病にかかったパキラは助かりません。基本的な改善方法がなく、そのままにしておくと他の植物に感染する危険性があります。そのため、感染したパキラは処分するほうが良いでしょう。白絹病になったパキラの処置方法
白絹病になったパキラの処置方法として、パキラの焼却処分と発生してしまった土の消毒、天地返しをする方法があります。他の観葉植物が感染しないように焼却処分する
白絹病になったパキラは株本ごと取り除き、焼却することで他の植物への感染を防ぎます。すぐに土の入れ替えを行うこと
白絹病になると菌は菌核をつくります。白絹病を発見し早急に取り除いても、目に見えない菌核が土の中に広がります。菌核を放置しておくと菌が長生きし、約5年ほど土の中で生存します。そのため、土の入れ替えを行うことが大切です。白絹病になった土は黒いビニール袋などで覆い、日光に当てることで消毒効果が期待できます。 また、菌核は土の表面上でしか生きられない生態をもっています。したがって、その生態を利用して土を深いところから掘り起こし、病気が発生した土を深い所に埋める天地返しをすることによって繁殖を抑えることが可能です。パキラの土が白いときによくある質問
パキラの土が白くなる原因や環境、対策予防についてここまでお伝えしてきました。ここではパキラに土が白いときに関してよくある質問にお答えしていきます。Q. パキラの土にカビが発生するのは、基本的に梅雨などの湿度が高い時期ではないんですか?
A,梅雨時期に限らずカビは発生します。 梅雨など湿度が高い時期はもちろんカビは発生しやすいです。しかし、住宅環境が良い方向へ進んでいるため、冬の室内は温かく結露ができるほどの湿度ある住宅が多いです。そのため、温度が20〜35℃、湿度が80%前後、エサとなる汚れや酸素など、条件を満たした環境になるとカビが発生します。 5月末から7月に多い梅雨の時期だけではなく、秋や冬の時期も注意が必要です。Q. 土にエタノールやお酢を散布するとph値が変わると思うんですが、大丈夫なんですか?
A,注意が必要です。 カビの殺菌に使われるエタノールやお酢ですが、土についた白いカビに吹きかけることによって土のph値が変わる可能性があります。吹きかけすぎはパキラにも影響しますので、吹きかけるときは注意してください。Q. そもそもパキラのカビってどこから飛来してくるんですか?
A,住宅建築や掘削作業によってカビ胞子が空中に飛来 元は土の中でカビ胞子や菌糸の状態でカビは存在します。土には微生物や養分を多く含まれ、カビに適した環境になっています。住宅建築の工事や堀削作業によって土が掘り返されることでカビが空中に飛来します。 空中で舞ったカビ胞子は、新しい場所へと飛来し落下したところでカビが好む環境になることでカビが発生する形になります。パキラの土が白い正体は何?病気なの?原因から対策方法を徹底解説のまとめ
ここまで、パキラの土に覆われた白いカビの原因や対処法についてお伝えしてきました。 パキラにできた白いカビの原因や対処法などをまとめると以下の通りになります。- 土についた白いものは白いカビは発生している
- 土が白く覆われる原因はカビが好む環境ができている
- 白いカビは毎日吸い続けることでアレルギーの原因になり人体へ悪影響を及ぼす
- 白く覆われた土やパキラの対処法は白いカビにはお酢やエタノール消毒をすることやカビが嫌う環境をつくる
- パキラは白絹病やうどんこ病などの病気になる可能性があるので注意が必要