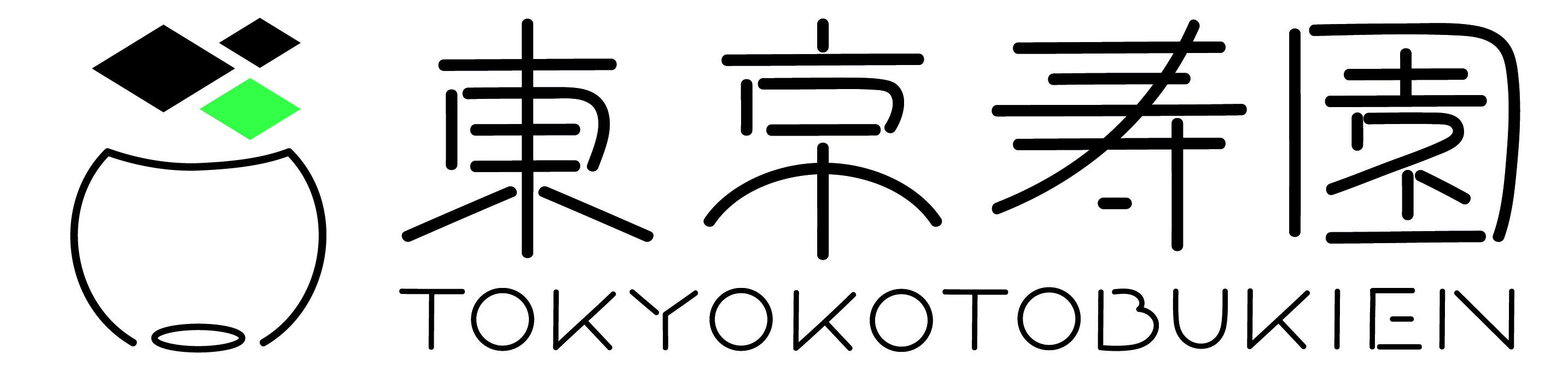風にそよぐ青い葉が美しいテーブルヤシ。管理も簡単で100均でも購入できる手軽さから、育てている方も多くいますよね。そんなテーブルヤシに虫が発生したらどのように対処すればいいのかあなたはご存知ですか?間違った対応をすると、
テーブルヤシが枯れてしまう こともあるので、しっかりと確認しておきたいですね。
今回は
テーブルヤシに虫が付く原因と虫の種類
テーブルヤシに付く虫の駆除方法とコツ
虫を予防する方法
虫が付きにくいハイドロカルチャー栽培
をご紹介します。
あわせてテーブルヤシに虫が発生したときに使用できる、
おすすめの殺虫剤4選 もご案内します。テーブルヤシに付く虫についてよくあるQ&Aも集めましたので、ぜひチェックしてみてくださいね。
この記事を読めば、テーブルヤシの虫を予防・駆除できるのはもちろん、 虫や病気に強い元気なテーブルヤシを育てることができます よ。
そもそもテーブルヤシに虫が付く原因とは?
そもそもテーブルヤシに虫が付く原因は何なのでしょうか。原因を知らなければ、駆除しても再び発生してしまうことも考えられますよね。しっかりと確認してみましょう。
湿気が多く、風通しが悪い
風通しが悪いと鉢の土が湿った状態が長く続き、虫が発生しやすい状態になってしまいます。多くの虫にとって
「暖かく、湿度があって風通しが悪い」状態が好条件ですが、これは室内で観葉植物を育てている環境と似ています ね。暖かくなり始めた多湿の時期は特に注意が必要ですよ。
茎や葉が乾燥している
葉や茎が乾燥しているとハダニが発生しやすくなります。 多湿を好む虫、乾燥を好む虫など、種類によって発生しやすい条件が違うのですね。乾燥しやすい冬場などは、葉の表面だけでなく葉の裏もよく観察してみましょう。乾燥対策としては
霧吹きで葉水 をしてあげるのがおすすめ。水やり方法については後ほど詳しくご紹介します。
受け皿に水が溜まっている
受け皿に水が溜まっていると、観葉植物付近の湿度が上がり、虫が発生しやすくなってしまいます。他にも
受け皿に水アカがついて汚れている のも虫が好む環境です。
受け皿に溜まった水は、水やりのたびに捨て、清潔を保っておくのがいいでしょう。 テーブルヤシに付く虫の種類
テーブルヤシによく付く害虫の種類をまとめてみました。観葉植物の現在の症状とあわせて確認してみると分かりやすいと思いますので、ぜひあなたのテーブルヤシと比べてチェックしてみてくださいね。
葉が脱色している:【ハダニ】
葉が脱色したり、点状に白くかすれているような時は、ハダニが発生しています。ハダニは体長0.5㎜ほどしかなく、肉眼でもほとんど気づかないくらい小さな虫。その小ささと被害の進行がゆっくりなため、
初期は気づけない ケースが多くありますよ。
葉が白くかすれてきたり症状が出てきた時は、すでに大繁殖していることもあります ので注意が必要です。
粉っぽい白い綿状の塊:【カイガラムシ】
テーブルヤシの枝などに
粉っぽい白い綿状の塊 が付いている時は、カイガラムシが発生しています。体長は3㎜ほどなので、よく観察すれば目で確認できます。カイガラムシが発生すると、葉がベタベタしたりすることも。
カイガラムシのフンはすす病などの病気を誘引することもあるので、早めの対策が必要です。 葉を痛める:【ナメクジ】
食べられる所ならどこでも食べて葉を痛めるナメクジ。小さな体のわりに食べる量が多いので、ナメクジが発生すると葉の大半を食べられてしまうことも。日中は暗い場所に隠れ、夜になると活動する夜行性なので、夜に確認すると発見できます。
生長点を食べられてしまうと、新しい葉が出てこなくなり、最悪の場合枯れてしまうこともありますよ。 葉を食べることもある:【ダンゴムシ】
柔らかい芽や新しい葉を食べることもあるダンゴムシ。
特に屋外の地面近くで管理しているテーブルヤシは注意が必要 ですよ。食害される可能性はナメクジの方が高いですが、ダンゴムシでも
葉を痛める可能性 があるので、気をつけたいですね。
葉だけでなく茎まで食べる:【バッタ】
バッタは葉の柔らかさに関係なく、大量に食害する害虫 です。葉だけでなく茎を食べることもあるので、放置するとテーブルヤシの大半が食べられてしまうことも。葉や茎に食害の跡があればナメクジ・ダンゴムシ・バッタを疑いたい所です。
テーブルヤシに付く虫の駆除方法
テーブルヤシにつく虫の種類をご紹介してきました。続いてそれぞれの虫の詳しい駆除方法を解説します。すでに発生してしまった虫は、早め早めの対応が大切ですよ。
【ハダニ】
ハダニの駆除方法は5つあります。
葉水を行う
鉢ごと水に浸す
木酢酢や牛乳を散布する
茎や葉をカットする
殺虫剤を散布する
ハダニは高温・乾燥の環境を好みますので、毎日の予防法として葉水を行うのが効果的です。 思い切って鉢ごと水に浸すと、土の中に潜んでいた幼虫や卵が浮いてくるので簡単に駆除できます。また牛乳の散布は、牛乳が乾燥する時にハダニが窒息するので有効ですし、木酢酢は観葉植物の生育環境を整えるメリットも。しかしどちらも匂いが残りやすいのが難点です。葉や茎のカットはハダニ発生の初期で、狭い範囲の時に有効でしょう。
【カイガラムシ】
カイガラムシの駆除方法は成虫と幼虫で対応が変わります。テーブルヤシの枝などに付く粉っぽい
白い綿状の塊は成虫 です。今回は成虫に対しての駆除方法をご紹介しますね。
カイガラムシの成虫は、貝殻のような殻をかぶっており、粉状の物質で殺虫剤をはじくため、効果が得られにくいと考えられます。ですから
直接綿棒や歯ブラシでこすり落としたりするのがおすすめ ですよ。植物の成長点でなければ、思い切って剪定してしまうのもいいでしょう。剪定する場合は、可能であれば成長期である5月~9月までに行います。
【ナメクジ】
ナメクジの駆除方法は3つあります。
塩をまく
熱湯をかける
殺虫剤を散布する
塩をまくとナメクジが脱水症状を起こします。熱湯はナメクジのたんぱく質を固めて駆除する方法で、どちらも大変手軽ですが、観葉植物に影響を及ぼす可能性もあるので注意が必要ですよ。
確実に駆除したい方はナメクジ用の殺虫剤を散布するのがいいでしょう。 【ダンゴムシ】
ダンゴムシの駆除方法で1番効果的なのは、殺虫剤を散布することです。 お子さんやペットがいて殺虫剤に抵抗がある方は、普段の予防策に力を入れておきましょう。ダンゴムシは湿度の高い環境を好みますので、
風通しの良さ を心がける といいですね。
【バッタ】
バッタの駆除方法は4つあります。
殺虫剤の散布
木酢酢の散布
トウガラシスプレーの散布
防虫ネット
確実に早く駆除したい場合は殺虫剤がオススメです。 化学的な薬剤を避けたい場合は、木酢酢やトウガラシスプレーもいいですね。木酢酢やトウガラシの刺激でバッタを寄せ付けない効果があります。また駆除した後に
防虫ネット をして再発しないようにするのも効果的です。
テーブルヤシに付いた虫の駆除のコツ
ここからテーブルヤシに付いた虫を駆除するときのコツをご紹介します。毎日のお世話の中でしっかり観察するべきポイントや、殺虫スプレー等で効果を得られない時の対処法を解説しますよ。
虫は葉の裏にもわくことがあるので念入りにチェック
虫は葉の表面だけでなく、葉の裏にわくこともあるので念入りにチェック しましょう。葉の裏は薄暗く虫にとって居心地のよい場所と言えます。霧吹きで葉水を行う際は、
葉の裏 までしっかり濡らしてあげるのがポイントですよ。
殺虫スプレー等で効果がない時は、テーブルヤシごと植え替えでもOK!
害虫の種類によっては、殺虫スプレー等で効果を感じられない時もあるかもしれません。虫の発生原因が土にありそうな場合は、表面から深さ5㎝の土を取り除き、無機質の土に替えてみましょう。それでも効果が感じられなければ、
思い切ってテーブルヤシごと植え替えてみてもOK です。植え替えは株分けの際だけでなく、害虫対策としても有効ですよ。時期はテーブルヤシの成長が活発な
5月~6月の間 に行いましょう。園芸店やホームセンターには、虫がわきにくい「室内向けの土」も販売されています。土に卵を産み付け繁殖する悪循環を断ち切ることができますよ。
何よりも観葉植物の状態を毎日確認すること!
駆除のコツとして何よりも大切なのは、普段の観葉植物の状態を毎日確認しておくことです。そうすることで
ちょっとした変化に気付くことができ、異常があっても早めに対処できます ね。虫の繁殖スピードは早いことが多いですから、早めに対応することがポイントになってきます。水やりや葉水のついでに、葉や茎、土の状態などをしっかり観察しておくといいでしょう。
テーブルヤシの虫除けにおすすめの商品
観葉植物の状態を毎日しっかりチェックしていても、虫がわいてしまった時。さまざまな対応策を行っても虫が完全に駆除できないときは殺虫剤を使用してみましょう。おすすめの商品4選をご紹介します。
住友化学園芸 殺虫殺菌剤 ベニカXファインスプレー
害虫に対して素早い効き目と持続性を持つベニカXファインスプレー。 殺虫作用だけでなく、スプレーすることで病原菌の侵入も防ぎ、病気を防除できます。逆さまでも噴霧できるので、葉の裏までまんべんなく散布できますよ。希釈せずそのまま使用できるのは、初心者にも使いやすい嬉しいポイント。希釈の割合で迷うことなく使えますし、薄める容器を準備する手間もかかりません。殺虫剤の有名メーカーである住友化学園芸の商品なので安心して使用できますね。
商品名
住友化学園芸 殺虫殺菌剤 ベニカXファインスプレー
価格
973円
成分
クロチアニジン・フェンプロパトリン・メパニピリム
特徴
害虫がいるポイントを狙ってスプレーできる手軽な1品。幅広い種類の植物に使えるので1本持っておくと安心。園芸初心者から上級者まで幅広い方に便利に使用できます。
amazonで詳細を見る
住友化学園芸 殺虫剤 MY PLANTS 虫からやさしく守るミスト
MY PLANTS 虫からやさしく守るミストは、
おしゃれなデザイン と確かな効果で人気の殺虫剤の1つです。
即効成分と浸透移行性成分の2つの成分を配合し、カイガラムシや葉の裏に隠れた害虫までしっかりと駆除 してくれます。他の殺虫剤と同様、使用時はマスクや手袋が必須ですが、それも確かな効果があるからこそ。見た目のおしゃれにこだわりつつ、確実な効果を実感したい方におすすめです。
商品名
住友化学園芸 殺虫剤 MY PLANTS 虫からやさしく守るミスト250ml 観葉 カイガラムシ
価格
800円
成分
フェンプロパトリン、クロチアニジン
特徴
ナチュラルなパッケージは、出しっぱなしにしても悪目立ちしないおしゃれなデザイン。観葉植物の近くに置いておけるので、気になった時にいつでもサッと使えます。
amazonで詳細を見る
住友化学園芸 殺虫剤 オルトランDX粒剤 200g
アセフェートとクロチアニジンの2種類の殺虫成分を配合したオルトランDX粒剤。
土にばらまくだけで、殺虫成分が根から株全体に行き渡ります。 葉や茎にも殺虫成分が移行するので、植物全体で殺虫効果を持つことになり、虫除け効果も期待できますね。株分けをする際や植え替え時に土に混ぜ込むか、土の上にまいておくだけでいいので、とても簡単に害虫対策ができますね。
商品名
住友化学園芸 殺虫剤 オルトランDX粒剤 200g 浸透移行性 アブラムシ コガネムシ幼虫
価格
953円
成分
アセフェート・クロチアニジン
特徴
粒状の本商品は、土にばらまくだけでいいので、手が汚れにくくとても手軽です。土の中にいる害虫にも効果があり、根を食害されないため植物の育ちもよくなりますよ。
amazonで詳細を見る
アースガーデン 園芸用殺虫剤 土にまくだけ害虫退治オールスター 150g
観葉植物だけでなく、花や野菜まで幅広く約300種の植物に使用できる土にまくだけ害虫退治オールスター。1本あればあなたのグリーンライフを支えてくれることでしょう。殺虫剤は独特のニオイがある製品が多いですが、本品は
ニオイ少な目で、集合住宅のベランダや室内で育てる観葉植物にも使いやすい ですよ。害虫が発生してからの散布でも効果が期待できますし、発生前に散布しておけば虫除け効果も期待でき、害虫を見ないで済むので助かりますね。
商品名
アースガーデン 園芸用殺虫剤 土にまくだけ害虫退治オールスター 150g
価格
800円
成分
ジノテフラン
特徴
1プッシュで約1gなので面倒な計量いらずです。殺虫剤のまきすぎが心配な方も安心して使えるので便利ですよ。
amazonで詳細を見る
【未然防止】テーブルヤシを害虫から守る育て方
テーブルヤシはたくさんの茎が土から立ち上がる育ち方であり、葉もたくさん茂るので株が蒸れやすいと言えます。そのため、
とくに春から秋は、虫や病気が発生しやすくなります よ。どのような環境で育てたらテーブルヤシを虫から守れるのか、毎日のお世話について詳しく見ていきましょう。
置く場所は【日当たり】【風通し】がいい所に!
テーブルヤシの置き場所は、日当たりと風通しがよい場所がおすすめ です。日当たりがよく暖かい場所が好きなのは、テーブルヤシの原産がメキシコやグアテマラなどの暖かい地域だからですね。日光が好きですが、葉が細く葉焼けしやすいため、1年中を通して
直射日光が長く当たるのは避けてあげましょう 。また風通しが悪いと土が濡れた状態が長く続き、虫が発生しやすくなってしまいます。室内と屋外の適した置き場所についてそれぞれ確認してみましょう。
室内での置き場所
室内で管理しているテーブルヤシは、明るい場所に置いてあげるのがいいでしょう。直射日光が当たりすぎると
葉焼け を起こし、最悪の場合枯れてしまうこともあるので気をつけます。葉の色が薄い時は、日光不足のサイン。そんな時は徐々に日光量を増やしてあげますよ。
レースカーテン越しの柔らかな日差しが当たるような場所がベスト ですね。
屋外での置き場所
テーブルヤシは耐陰性があり強い日光が苦手です。葉焼けも起こしやすいため、
半日陰か午前中だけ直射日光の当たるような場所がいい でしょう。もしくは
寒冷紗などで軽く遮光 してもOK。どちらも風通しのいい所に置くようにしてくださいね。
水やりは季節ごとに変える
元気なテーブルヤシを育てるために、水やりにも気を配りたいものです。水やりは季節ごとにタイミングや量を変えるのがポイントですよ。
春~夏にかけての水やり
テーブルヤシは多湿を好む植物です。したがって
春~夏にかけての水やりは、土の表面が乾いたら鉢底から水が流れるほどたっぷりと与える のがいいでしょう。常に土が濡れていると根腐れや病害虫の原因になるので、テーブルヤシ周辺の湿度を上げる葉水で調整していきますよ。
葉水は1~2日に1回程度 行います。水不足になると葉っぱがしおれてくるので、育てながら水やりのタイミングをつかんでいきましょう。
秋~冬にかけての水やり
秋~冬はテーブルヤシの休眠期間に当たります。この時期は水を吸う力も弱くなるので、水やりの間隔を空けていきましょう。
根腐れを防止するためにも、 頻度は2週間に1回程度で、やや乾燥気味に管理 します。1~2日に1回程度、葉っぱの裏まで
葉水 をしておくことで、乾燥やハダニなどの害虫防止ができますよ。
土は水はけがいいものを使う
テーブルヤシには根腐れを防止するためにも、水はけのいいものを使うのがおすすめ ですよ。市販されている
観葉植物用の土 でもいいですし、自分でブレンドしたい場合は
「観葉植物用の用土4:赤玉土1:鹿沼土1」 の割合で混ぜます。土の表面を赤玉土や鹿沼土、化粧砂などで覆えば、害虫予防にもなりますよ。
肥料は成長期に与えるようにする
肥料は成長期である暖かい季節に与えるようにします。
2ヶ月に1回程度、緩効性肥料の置き肥を与えるか、2週間に1回程度液肥を与えましょう。 冬場はテーブルヤシの休眠期に当たります。株全体の活力が弱まっているので、
冬場の肥料は必要ありません 。この時期に肥料を与えると、肥料を薄めようと根から水分を放出して、かえって水不足になる「肥料焼け」が起こるからです。また植え替えを行った後も、根が養分を吸いあげる力が弱まっているため、2週間程度開けてから肥料を与えるようにしましょう。
テーブルヤシに虫が付きにくいハイドロカルチャー
「とにかく虫が苦手…。」「虫の付きにくい栽培方法ってないのかな?」そんな風に悩んでいるあなたにぴったりの栽培方法がハイドロカルチャー栽培です。テーブルヤシはハイドロカルチャー栽培も可能ですよ。詳しく見てみましょう。
ハイドロカルチャーは虫がわきにくい栽培方法
ハイドロカルチャーは、発砲煉石(はっぽうれんせき)と呼ばれる人工の土
「ハイドロボール」 を利用した栽培方法のことです。ハイドロボールには細かい穴が無数にあり、この中に空気や水を取り込んで植物に栄養を与えますよ。ハイドロボールは高温で焼いて作られているので、基本的には無菌です。
土の有機物が原因で発生する害虫もわきにくいため、虫が付きにくい栽培方法 と言えますよ。
ハイドロカルチャーのテーブルヤシは初心者でも安心
ハイドロボールは、無数にある穴に水をため込むことができます。そのため
頻繁な水やりは不要で、忙しい方でも手軽に植物を育てることができます 。また透明の容器を使えば、見るだけで水の量が把握できるので管理もしやすく、初心者でも安心してテーブルヤシを育てられますよ。土を使いたくないキッチンや寝室などにも置けるので、様々な場所でテーブルヤシを楽しむことができますね。
ハイドロカルチャーへの植え替えに必要なもの
土栽培からハイドロカルチャーへの植え替えに必要なものを見ていきましょう。事前に準備することで、植え替えもスムーズに進みますよ。植え替えた時に容器内の水をきれいに保てるので、
ハイドロボールはあらかじめ水洗いしておくことがおすすめ です。
あらかじめ水洗いしておいたハイドロボール
根腐れ防止剤
水耕栽培用の液体肥料
底に穴の開いていない容器
割りばし
水位計
前述のとおり、ハイドロボールは基本的に無菌です。根の老廃物を分解する微生物もいないので、根腐れ防止のために
根腐れ防止剤 を底に敷いておきましょう。植物に対する栄養として液体肥料も必要です。またハイドロカルチャー栽培は、根が常に水に浸っていることが多く、構造としては根腐れが起きやすい状態と言えます。水やりのタイミングを確認するためにも、初心者の方は水位計があると分かりやすいですよ。
ハイドロカルチャーへの植え替え手順
土栽培からハイドロカルチャーへの植え替え手順をご紹介します。
植え替えに適した季節は、成長期である春~夏 です。冬場は株の力が弱まり、根の活着が悪くなるので避けた方がベターですよ。
植え替える容器に、底が隠れるくらいの量の根腐れ防止剤を入れる。
ハイドロボールを容器の1/4程度入れる。
元の鉢からテーブルヤシを優しく抜き、軽く土を落とす。土が落ちにくい場合は水に漬けて、優しくふるって落とす。
新しい容器とのバランスを見ながら株を配置し、さらにハイドロボールを追加する。この時割りばしで優しくつつきながら入れていくと空間ができにくい。
新しい容器の1/5程度まで水を入れる。
液体肥料を入れるのは、成長期である春~夏にかけて です。
2週間に1回程度 、水やりのタイミングで一緒に与えるといいですね。
テーブルヤシに付く虫についてよくある質問
テーブルヤシに付く虫についてよくある質問をまとめてみました。観葉植物を育てていると虫とはなかなか縁が切れにくいもの。ぜひ参考にしてみて下さいね。
Q. テーブルヤシの土に小さい白い虫がたくさんいます。これはトビムシかなにかですか?
A,飛び跳ねる小さな白い虫はトビムシの可能性が高いです。
トビムシは体長2~3㎜程度の小さな虫です。観葉植物の土中やその近くに潜み、水やりや、鉢が揺れるなどの衝撃で一斉にジャンプしますよ。病気を引き起こしたり、他の害虫を誘引することはありませんが、大繁殖すると不快なため早めに駆除するのがおすすめです。原因は水やりのしすぎや、水はけの悪さ、観葉植物の付近に残った落ち葉や土のカスなど。殺虫剤などで駆除するのももちろんいいですが、
生育環境を見直す ことも大切です。
Q. テーブルヤシの根元にカビらしきものがあります。何が原因ですか?
A,過湿と風通しの悪さが原因です。
テーブルヤシは多湿を好む植物ですが、過湿と風通しが悪いとカビが生えてしまうことがあります。カビ自体は歯ブラシなどでこすり取りましょう。しばらく水やりは控え、風通しのよい場所に移してあげます。それでも効果がなく再度カビが生えてしまったら「ロブラール」などの殺菌剤で消毒してあげるのがおすすめです。
Q. テーブルヤシの葉の表面に白い液体か何かの乾いた跡があります。これは虫の痕跡でしょうか?
A,汚れまたはカイガラムシ両方の可能性があります。
水のカルキ成分や肥料などが葉の表面に白く残るケースも考えられます。その時は濡れた布などで優しく拭き取ってあげましょう。それで取れれば「汚れ」ですので、心配はいりません。拭き取っただけで取れない場合は、
カイガラムシ の可能性があります。カイガラムシは前述の駆除方法の通り、歯ブラシや綿棒などでこすり落としましょう。カイガラムシのフンはすす病などを誘発するので、しっかりと駆除します。暗くほこりっぽい場所で繁殖しやすいので、明るく風通しのよい場所に置きかえてあげましょう。
テーブルヤシに付いた虫の駆除方法!日頃のケア方法まで徹底解説のまとめ
テーブルヤシに付く虫について、駆除方法や毎日のケア方法までご紹介してきました。
本記事では
虫が付く原因として、多湿と風通しの悪さ、葉や茎の過度な乾燥、受け皿に溜まった不潔な水などが考えられる
テーブルヤシにはハダニ・カイガラムシ・ナメクジ・ダンゴムシ・バッタなどが付きやすい
予防策として普段からよく植物を観察し、毎日葉水を行うと良い
殺虫剤などが効かない時は、用土を新しくして植え替えをするのもアリ
テーブルヤシは日当たりと風通しのよい場所を好み、健康な株は病害虫の被害にもあいにくくなる
テーブルヤシに虫が付きにくいハイドロカルチャー栽培もおすすめ
についてご紹介してきました。
大切に育てていたテーブルヤシに虫が付いていたらびっくりしてとても不快になると思います。一度落ち着いてよく観察し、それぞれの虫によって違う対処法を試してみて下さいね。
虫を大繁殖させず、テーブルヤシにも負担なく駆除するためには、早め早めの対応がポイントですよ。
最後まで読んでいただきありがとうございました。東京寿園では他にも様々な観葉植物についての記事を掲載しています。ぜひ他の記事も参考にしてみてくださいね。