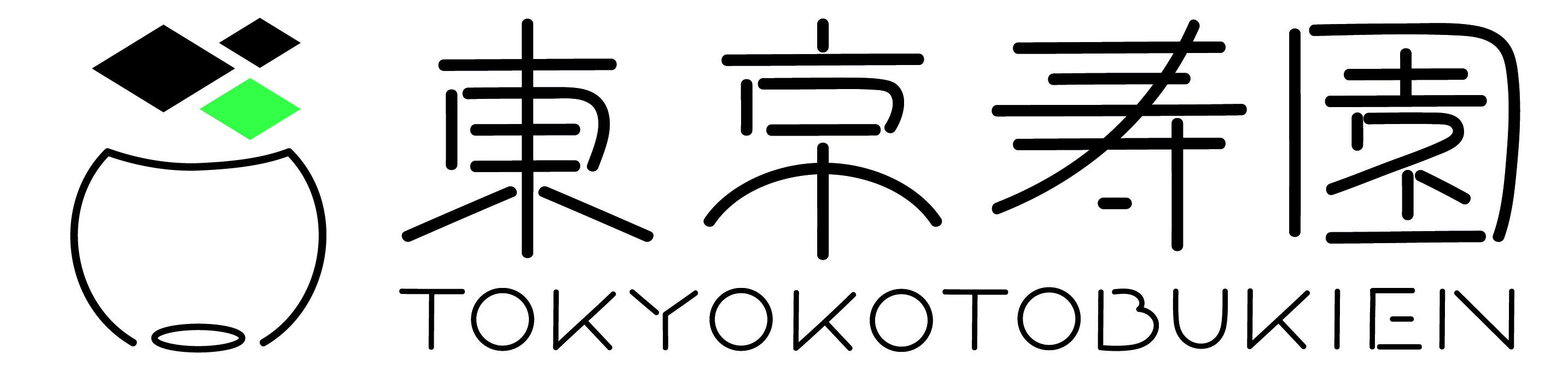ガジュマルはぷっくりとした幹の形が神秘的で、インテリアとしても人気が高い植物ですね。また育て方が簡単で初心者でも管理がしやすく、ガジュマルは虫がつきにくい植物ともいわれています。 しかしながら、もちろん全く虫がつかないというわけではありません。あなたは、ガジュマルに虫がついてしまった時の駆除方法や予防法についてご存じでしょうか。これらの対処法について知っていれば、日頃から虫の発生を予防しながら元気なガジュマルを楽しむことができますよね。
そこでこの記事では
- どうしてガジュマルに虫が付くのか?
- ガジュマルによく付く虫と駆除法は?
- ガジュマルの虫除けにおすすめの商品は?
- ガジュマルに虫を寄せ付けないケア方法は?
について解説していきます。 この記事を読んでいただければ、ガジュマルに虫を発見してしまった時もスムーズに駆除できるだけでなく、日頃からガジュマルに虫がつかないための対策も学ぶことができます。後半ではおすすめの殺虫剤も紹介していきますので、ぜひ最後までお読みください。
どうしてガジュマルに虫が付くのか?
大切に育てていたのに、ガジュマルに虫がついていたらショックですよね。どうして、ガジュマルに虫がついてしまうのでしょうか。 主に
3つの原因が考えられますので、あなたの育てているガジュマルの環境が当てはまってしまっていないかチェックしてみてください。
①風通しが悪く、湿気がこもりやすくなっている
ガジュマルの葉や株が密集していたり、風通しの悪い部屋に置いていると、湿気が溜まってしまいます。
湿気を好む害虫が発生する可能性が高まりますので、適宜剪定を行ったり、風通しの良い場所に移動させてください。
②茎や葉が乾燥している
湿気が溜まることも良くありませんが、
乾燥も害虫の発生を引き起こします。茎や葉が乾燥しているとそれを好む害虫が寄ってきます。特に冬場は空気が乾燥し、気づいたら、茎や葉が乾燥していることもありますので、
定期的に葉水を行い、適度に湿度を保つようにしましょう。
③受け皿に水が溜まっている
受け皿に水が溜まっていると、ガジュマル周辺の湿気が高くなり、根腐れを起こすばかりか、虫が発生しやすくなります。
受け皿に溜まっている水に卵を産み付け、そこから虫が湧いてしまいます。受け皿には
水を溜めずにすぐ捨てるようにしましょう。
ガジュマルによく付く虫と駆除法①:アブラムシ
アブラムシは、
春先から初夏にかけてガジュマルに付くといわれる虫です。体長が1~4mmほどの小さい虫ですが、
非常に繁殖力が強い虫です。
新芽や若葉に付きやすく、黒い点が少し動くようであれば、アブラムシの可能性があります。
特徴:葉が茶色、黒い状態になる
アブラムシは、若い葉や新芽に寄生し吸汁しガジュマルの葉は黄変、または
茶色く変色させてしまいます。また、葉に甘露と呼ばれるアブラムシの排泄物が堆積すると、
すす病と言われる
病気で黒くなってしまいます。
駆除方法:殺虫剤や牛乳スプレーを行う
アブラムシは繁殖力が強いので、
発見したらすぐに対処しなければいけません。
牛乳をスプレーし、牛乳の膜でアブラムシを窒息させるという駆除方法があります。また、すでにアブラムシが
大量発生してしまっている場合は、殺虫剤を使用することをおすすめします。
ガジュマルによく付く虫と駆除法②:ハダニ
ハダニは赤、または
黒い小さな虫で体長は0.5mmほどしかありません。ハダニは乾燥を好み繁殖しますので、暖かく乾燥しがちな室内にガジュマルを置いている場合は、注意が必要です。 また、卵を産む数も多く成虫になるスピードも早いので、ハダニを見つけたらすぐに対処してください。
特徴:葉に無数の白い斑点ができる、糸を引いている
ハダニは、
葉から養分を吸って植物を枯らしてしまいます。葉に無数の白い斑点ができ、被害がに広がると植物の成長を妨げ枯れてしまいます。 また、ハダニは体長0.5mmほどで、
被害もゆっくりなことからよく注意しておかないと
見つけるのが遅れやすいといわれています。ハダニは葉っぱの上の住処や卵を守るために糸を出しますが、この白い糸を引いていたら、葉の裏にはすでにハダニが大量発生しているでしょう。
駆除法:殺虫剤を散布する、葉水を行う
ハダニは水に弱い害虫なので、
葉水はハダニの駆除に有効です。シャワーの強い水流で葉についたハダニを流すことも効果的です。 また、大量発生している場合は、ハダニ専用の殺虫剤を葉の表裏に丁寧に散布します。しかしながら、ハダニは耐薬品性がつきやすいので、
複数の薬剤をローテーションして使用する必要があります。
ガジュマルによく付く虫と駆除法③:蛾の幼虫
ガジュマルに毛虫がつくことがありますが、それは蝶または、
蛾の幼虫である事が多いです。4月~11月頃に発生し、
毒を持つ幼虫もいるので触れないように注意が必要です。
特徴:葉が虫食いになる
蛾の幼虫が付くと、葉を食べてしまいガジュマルの葉が
虫食いの被害にあってしまいます。蛾の幼虫は
葉の裏側に潜んでいることが多く、葉の虫食いや蛾の幼虫を見つけたら、下記の駆除方法を実践してみましょう。
駆除法:殺虫剤を散布、木酢液をスプレーする
毒を持っている蛾もいるとお伝えしましたが、毛虫に触れずに駆除できるため、薬剤散布がおすすめです。
毛虫に効果がある殺虫剤を散布すると良いでしょう。 また、ペットや小さなお子様がいるご家庭では、こういった殺虫剤を使うことに抵抗がある方もいらっしゃるかもしれません。そういった場合は、木炭が原料となっている
木酢液をスプレーするのもおすすめです。 殺虫剤などをスプレーすると、
毛虫の毒毛針が飛散する可能性がありますので、念のためマスクやゴーグル、手袋などを着用してください。
ガジュマルによく付く虫と駆除法④:カイガラムシ
ガジュマルの害虫として
カイガラムシもよく見られます。カイガラムシは茶色く小さい虫で、吸汁によって
植物の生育不良を起こしたり、病気も引き起こします。春から夏にかけて見つかることが多く、枝葉が茂った状態で
風通しが悪くなると発生しやすい害虫です。
特徴:白い綿状の塊を見つける
カイガラムシが葉や茎に付着している場合、
白い綿状の塊が見られます。カイガラムシは体から分泌物を出し、その分泌物であるロウ物質や白い粉で体表面を覆っているためです。
対処法:直接取り除く
カイガラムシの発生初期は、
直接取り除くことで十分対処できます。
布、
ティッシュペーパー、
歯ブラシなどで優しくこすり落としてみましょう。カイガラムシは水に弱いため、こすり落とす
布や歯ブラシなどを濡らしておくのもおすすめです。
ガジュマルによく付く虫と駆除法⑤:コバエ
コバエは、暖かく湿った
梅雨の時期などに発生しやすい虫です。ガジュマルに与えた肥料や、ガジュマルを植えている土に
腐葉土や
堆肥が含まれていると、それを養分にして繁殖を繰り返すといわれます。
特徴:根っこの周りに飛ぶ
ぶんぶん飛ぶコバエは網戸からも侵入できるほど小さく、植物の周りを飛ぶので、うっとうしく感じる方も多いでしょう。ガジュマルの土に付くと、土の表面から深さ3cmほどのところに卵を産み付けます。室内で育てていると
土が暖かく湿った状態になりやすく、肥料などを養分にしているため、土付近の根元に発生しています。
対処法:土を入れ替えるのが効果的
コバエが発生する主な
原因は土です。 コバエは土の中に卵を産み付けるため、飛んでいるコバエだけでなく、
土の中にある卵も取り除く必要があります。そのため、コバエが発生しにくい
無機用土に植え替えるのが効果的ですが、赤玉土や、バーミキュライトなどがそれにあたります。
室内用と表記されている土や
観葉植物用の土を購入すると良いでしょう。 また、土を使わない
ハイドロカルチャーに植え替えることも一つです。ハイドロカルチャーは、ハイドロボール、ハイドロコーンといった多孔質の人工用土を使用するため、土を使わず室内でも清潔に育てられるといったメリットがあり人気の方法です。
ガジュマルについた虫の駆除のコツ
ガジュマルに付いた虫を駆除するコツを3点紹介します。ガジュマルのお世話をしながら日頃から取り入れられる簡単なことばかりですので、ぜひ押さえておきましょう。
①葉の裏にも湧くことがあるので念入りにチェックする
虫は葉の裏に潜んでいるため、殺虫剤を散布したり、葉水をする場合見えている
葉の表面や茎だけでは不十分です。葉の裏側も虫がついていないかしっかりとチェックしながら、スプレーしてください。
②殺虫剤やスプレー等で効果がない時は、植え替えてみる
ガジュマルに付く虫によって、水や殺虫剤など駆除方法は様々ですが、それらの方法で
効果が見られない時は、思い切って植え替えてみましょう。土中に虫の卵が産み付けられていたり、土の劣化によって常に湿った土になり虫が寄ってきやすい状態になっている可能性があるためです。
③観葉植物を毎日、チェックすることが重要
ガジュマルに付く虫は大体がとても小さく、網戸をすり抜けたり、風に乗って飛んできたりします。 葉の虫食いや葉の変色といった症状が見られたら、すでにガジュマルには虫が大量発生している可能性が高く、駆除も大変になってきます。そのため、
日頃のお世話のついでに葉の表裏や土の周りをチェックする癖をつけておくと、ガジュマルを虫の被害から守ることができるでしょう。
ガジュマルの虫除けにおすすめの商品
ここからは、ガジュマルの虫除けにおすすめの商品を4つご紹介します。どの害虫を防ぎたいかによって、有効成分が異なりますので、使用方法と合わせて参考にしてくださいね。
住友化学園芸 殺虫殺菌剤 ベニカXファインスプレー
害虫に対して、
速効性と持続性を兼ね備えたスプレータイプの殺虫殺菌剤です。また、病原菌の侵入も防ぎ病気予防にも効果的です。葉の裏や根元にもスプレーしやすい
逆さ散布も可能な容器で、花はもちろん幅広い植物に使用することができます。散布する際は、マスクやゴーグル、手袋等を着用してください。
| 商品名 |
殺虫殺菌剤 ベニカXファインスプレー 1000ml |
| 価格 |
973円 |
| 成分 |
クロチアニジン、フェンプロパトリン、メパニピリム |
| 特徴 |
花や緑の幅広い植物に使える殺虫殺菌剤 |
住友化学園芸 殺虫剤 MY PLANTS 虫からやさしく守るミスト
作用の異なる2つの殺虫成分を配合しています。
速効成分は、葉をべたつかせるカイガラムシに、
浸透移行性成分は、葉裏に届きアブラムシの退治に効果を発揮します。こちらの商品は、おしゃれなパッケージで、観葉植物のそばに置いていても、お部屋のインテリアも邪魔しません。
| 商品名 |
殺虫剤 MY PLANTS 虫からやさしく守るミスト250ml |
| 価格 |
800円 |
| 成分 |
フェンプロパトリン、クロチアニジン |
| 特徴 |
葉や枝、茎に発生する虫を退治するスプレー |
住友化学園芸 殺虫剤 オルトランDX粒剤 200g
こちらは、
土に混ぜ込むタイプの粒状殺虫剤で、初心者にも簡単に害虫を駆除することができる商品です。浸透移行性を2種類配合しており、殺虫成分が根っこから吸収され、葉や茎に行き渡るので、
葉に付く害虫だけでなく、土の中にいる害虫の駆除にも効果を発揮します。毛虫やカイガラムシなどの駆除におすすめです。
| 商品名 |
殺虫剤 オルトランDX粒剤 200g |
| 価格 |
953円 |
| 成分 |
アセフェート、クロチアニジン |
| 特徴 |
浸透移行性の殺虫成分を2種類配合した粒状殺虫剤 |
アースガーデン 園芸用殺虫剤 土にまくだけ害虫退治オールスター 150g
こちらは、土に撒くタイプの粒状の殺虫剤です。殺虫剤特有の嫌なにおいが無く、
散布器付きで手が汚れません。散布器がある事によって、
殺虫器剤の撒きすぎも防ぐことができ、定量撒くことができるので初心者にも使用しやすい商品です。アブラムシ類やコナジラミ類、ハモグリバエなどに効果を発揮します。
| 商品名 |
園芸用殺虫剤 土にまくだけ害虫退治オールスター 150g |
| 価格 |
800円 |
| 成分 |
ジノテフラン(RS)-1-メチル-2-ニトロ-3-(テトラヒドロ-3-フリルメチル)グアニジン、鉱物質微粉等 |
| 特徴 |
イヤなニオイがしない土にまく粒タイプの殺虫剤 |
【超重要】根本的にガジュマルに虫を寄せ付けないケア方法
ここまでは、ガジュマルに虫がついてしまった時の対処法について詳しく解説してきましたが、ここからは、根本的に
虫を寄せ付けない方法を4つご紹介します。日頃から実践することで、ガジュマルを虫の被害から守っていきましょう。
【日当たり】【風通し】がいいところに置く
ガジュマルを育てるうえで、日当たりや風通しを気にしている方は多いと思いますが、改めて、日当たりと風通しが良い場所にガジュマルを飾っているか確認してみましょう。 薄暗く湿気が溜まる環境にいるとコバエが発生すると前述しましたね。日当たりがあまりよくない場合は、
午前中だけ日当たりの良いところにガジュマルを移動する、風通しが良くない場合は
サーキュレーターを使用するなどの方法もおすすめです。
時期ごとに水やりの量やタイミングは変える
ガジュマルを育てている方は、「土が乾いたらたっぷりと水を与える」という育て方を実践している方が多いと思いますが、季節によっても
水やりの量やタイミングを変えることで、虫の発生予防につながります。
春・夏の水やり
春・夏(6月~9月頃)はガジュマルの生長期と重なるため、
土が乾いていれば毎日水をあげましょう。しかし日中の水やりは避けてください。気温の上昇とともに、植木鉢が蒸し風呂状態になってしまうので、ガジュマルの株に湿気が溜まってしまいます。
秋・冬の水やり
秋・冬は、ガジュマルが休眠期に入ります。ガジュマルの水を吸う力も穏やかになるので、水やりは控え乾燥気味に管理します。
土が乾いてから2~3日後に水を与えるイメージでお世話してみましょう。しかし、乾燥もまた虫の発生の原因になりますので、
葉の表裏に葉水を行ってください。
土は水はけがいいものを使う
室内でガジュマルを育てている場合、水やりの水分でどうしても多湿状態になりがちです。根腐れを引き起こしたり、虫も多湿を好んで寄ってきますので、
できるだけ水はけのよい土を使用するのがおすすめです。自分で赤玉土やバーミキュライトなどを混ぜて土づくりをすることもできますが、市販されている
「観葉植物用の土」はすぐに使用することができるのでおすすめです。
肥料はガジュマルの成長期にのみ与えるようにする
ガジュマルは、肥料が無くても元気に育つといわれています。肥料を与えたい場合は、ガジュマルの
成長期のみ、緩効性
化成肥料を与えてください。また、肥料には、有機肥料と化成肥料という種類があり、
有機肥料は虫が寄ってきたり繁殖する原因となるので、化成肥料を使用しましょう。
【豆知識】葉水はガジュマルに付く虫対策だけはない
ガジュマルをはじめ、多くの観葉植物のお世話の一つである葉水ですが、皆さんは葉水の役割をご存じでしょうか。実は虫対策効果だけではありません。
葉水を行うことのメリット3選
以下では、葉水を行うことのメリットを3つご紹介します。
ガジュマルに寄ってくる虫を落とすことが出来る
葉水によって、ガジュマルに付いた虫を洗い流すことができます。さらに、
水を嫌う虫は、葉が濡れていると植物自体に近寄らなくなりますので、病害虫の予防になります。
ガジュマルの葉や茎が乾燥することを防げる
観葉植物にとって乾燥は、
葉っぱが変色したり枯れてしまう原因となります。水やりからも水分を吸収しますが、葉水を行うことによって、
直接葉にも水分が行き渡り、湿度も保たれます。葉水によって葉がみずみずしくなるだけでなく、枯れや病気を防いでくれます。
ガジュマルの葉のホコリを落とすことが出来る
葉水を行うことで、
葉に付いたホコリを落とすことができます。ガジュマルを室内で育てているとベランダなど屋外で育てるよりもホコリがつきやすく、
付着したホコリによって日当たりが遮られ、光合成の妨げになります。
ガジュマルに葉水を行うときのコツ
葉水を行う際のコツがあります。これらを押さえて効果的に葉水を行っていきましょう。
葉水は葉だけではなく茎や幹にも行うと効果的
葉水は、葉っぱの表裏だけでなく、茎や幹にもしっかりと行うことで
ガジュマル全体の湿度が保たれます。ガジュマルは湿度が高めを好む植物のため、全体的に潤わせるように葉水を行ってください。
葉水のやりすぎは逆にガジュマルを痛めるので要注意
葉水は必要なお手入れの一つですが、
葉水の量が多すぎるとガジュマルが痛んでしまいます。適切な量とは、
全体に霧状に水が覆っている状態がベストです。逆に水滴が玉になっているのは葉水が多すぎる証拠です。葉水が多すぎた場合は、ティッシュペーパーやタオルなどで優しくふき取ってください。
ガジュマルに付く虫に関してよくある質問
ここからは、ガジュマルに付く害虫に関してよくある質問をご紹介します。
Q. ガジュマルの植木鉢に小さい虫がたくさんいました。これは何ですか?
A,ハダニの可能性が高いでしょう。 ハダニは0.5mmほどの小さい虫です。ハダニの駆除方法として、葉水や植木鉢ごと水に漬けるなど、水で洗い流すことは効果的ですが、洗い流してもたくさん発生するようであれば、
ハダニ専用の薬剤が入った殺虫剤や農薬を使用しましょう。散布する場合は屋外で行い、半日ほどおいてから室内に戻しましょう。また、ハダニは耐薬品性がつきやすいので、複数の薬剤を使うことも検討してみてください。
Q. ベランダでたくさんの観葉植物を育てているので、出来るだけ安全な薬剤を使いたいのですが、いいものはありますか?
h
A,お酢を使ったコバエ取り液を使用してみてはいかがでしょうか。 ベランダで育てている場合、近所や室内に殺虫剤などの薬剤の影響が出ないか気になる方も多いでしょう。こちらのお酢スプレーはコバエに効果があるといわれていますので、以下の材料を混ぜて、ペットボトルに少量入れて置いておくとコバエが確保できます。
- お酢 70cc
- 砂糖 100g
- お酒 50㏄
- 2Lの空ペットボトル
Q. ガジュマルの新芽が丸まることがあるのですが、これは害虫や何かの病気ですか?
A,水不足の可能性があります。 水不足が考えられます。ガジュマルをはじめとする観葉植物は、根っこから水分を吸収し、葉の先まで水分を行き渡らせます。 葉に届いた水分は、植物の乾燥具合や、気温等様々な要因に応じて葉から蒸散(大気中に水分を放出すること)しますが、植物の水分不足の場合、
葉の乾燥が原因で丸まるといった現象が起こります。丸まることで、日光に当たる面積を小さくしてダメージを最小限に抑えるためだといわれています。
ガジュマルに付いた虫はどうすればいいの?駆除方法から防ぐ方法を紹介のまとめ
いかがでしたか。ガジュマルに付く害虫の駆除方法や予防方法について解説してきました。 この記事のポイントは
- 虫がついてしまう原因は、「風通しが悪いく湿気が溜まっている」「乾燥している」「受け皿に水が溜まっている」の3つが考えられる
- ガジュマルに付く虫は、葉水や殺虫剤で駆除する
- 日頃から虫の発生を防ぐには、「日当たりと風通しの良い場所に置く」「時期に合わせた水やりを行う」「水はけのいい土を使う」「肥料は成長期のみ与える」の4つがポイントである
- 葉水は、発生した虫を駆除するほか、虫が寄ってくるのを防ぐこともでき、全体に霧が覆っているような状態が適切な葉水の量である
ということでしたね。 これらを押さえれば、発生した場合の駆除方法も押さえつつ、ガジュマルに虫が発生することを未然に防ぐことができます。ぜひ日常的に虫を寄せ付けないケア方法を取り入れて、ガジュマルを虫の被害から守りながら元気に育ててください。 最後までお読みいただきありがとうございました。TOKYO KOTOBUKIENには他にもたくさんの記事をご用意しておりますので、是非ご覧ください。