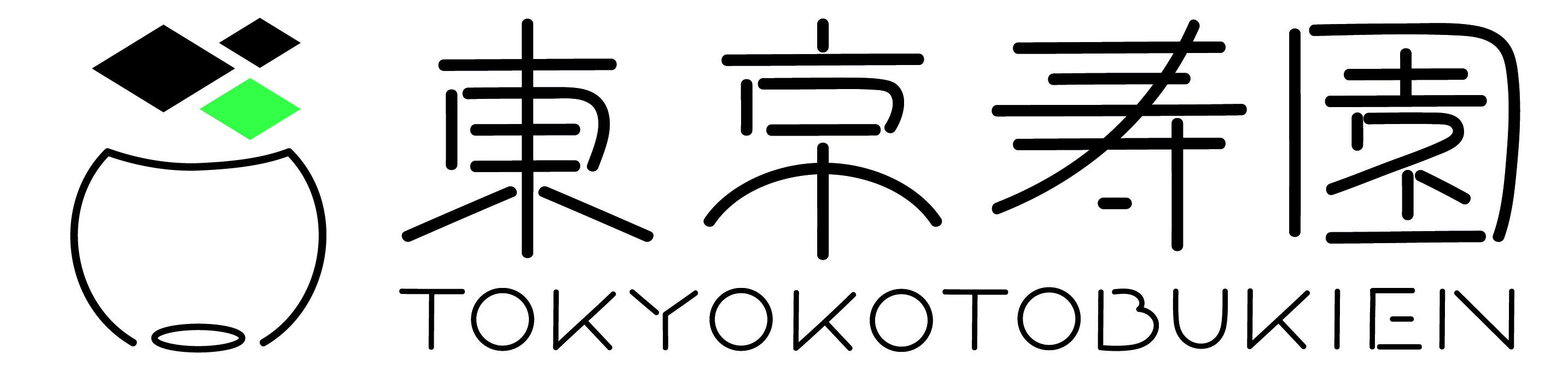目次
皆さんは観葉植物育てた経験はありますか?観葉植物は育てる楽しみもありますが、お部屋に飾ればグリーンインテリアとして癒しを与えてくれます。
今回はそんな観葉植物の品種の中でも比較的育てやすく人気の高いダイモンジソウ(大文字草)の育て方についてご紹介しています。育成難易度が低いと言われているダイモンジソウですが、育て方を大きく誤ってしまえば当然枯れてしまう可能性もあります。せっかく育てたダイモンジソウが枯れてしまっては大変ですよね。そこで本記事では以下の内容をまとめました。
- ダイモンジソウってどんな観葉植物?
- ダイモンジソウの育て方
- ダイモンジソウの植え替え
- ダイモンジソウの増やし方
- ダイモンジソウに考えられるトラブルと対処法
ダイモンジソウってどんな観葉植物なの?
まずダイモンジソウの育て方をご紹介する前にダイモンジソウの基本情報と特徴をご紹介しておこうと思います。ダイモンジソウをこれから育てようか悩んでいる方はぜひ参考にしてくださいね。ダイモンジソウの特徴
まず始めにダイモンジソウの特徴をご紹介していきますので気になる方は是非見ていってくださいね。山地の湿った岩場や渓谷の岩上に生える多年草
ダイモンジソウはユキノシタ科ユキノシタ属の多年草で原産地は日本、中国、朝鮮、サハリンとなっています。ダイモンジソウは乾燥を嫌う植物であるため、日本では山地の湿った岩場や渓谷の岩上に生えていることが多いです。 ここでは紹介していませんが、ダイモンジソウにも様々な品種があります。どれも個性豊かな見た目をしていますので、気になる方は調べてみてくださいね。大の字に見える花の形が特徴
ダイモンジソウの花は開くと星型に開き、下の2枚が他より長い花びらになることから漢字の『大』の文字に似ているという背景が『大文字草』の名前の由来になっているそうですよ。ダイモンジソウの花言葉
ここではダイモンジソウの花言葉についてご紹介していきます。ダイモンジソウには複数の種類の花言葉がありますので興味のある方はぜひご覧になってくださいね。自由
1つ目の花言葉は『自由』。これは人が『大』の字になって寝ている姿や大の字で背筋を伸ばしている姿が自由を連想することから付けられています。何か山場を乗り越えた知り合いや友人にこの花言葉とダイモンジソウをプレゼントするのもいいかもしれませんね。不調和
次に紹介する花言葉は『不調和』。これはダイモンジソウの花びらが理由となっており、ダイモンジソウの花びらは下の2枚だけ少し長くなっています。この見た目が不調和を連想させることからこのような花言葉がつけられました。情熱
次にご紹介する花言葉は『情熱』。こちらはダイモンジソウがよく岩に寄り添って咲いていることが由来となっているそうです。情熱がこもった相手にダイモンジソウを送ってみるのもいいかもしれませんね。好意
次にご紹介する花言葉は『好意』。こちらも『情熱』と同様にダイモンジソウがよく岩に寄り添って咲いていることが由来となっているそうです。好きな相手にダイモンジソウを使った花束をプレゼントしてみてはいかがでしょうか?節度
最後に紹介する花言葉が『節度』。こちらは岩上に咲いているダイモンジソウが土に汚れる事がほとんどない姿から連想されて付けられた花言葉です。節度を持った立ち振る舞いや真面目な友人に贈ったらきっと喜んでくれますよ。ダイモンジソウに目立った風水効果はない
植物には様々ないい効果が得られる、風水効果というものが良く存在しますがダイモンジソウに風水効果は特にありませんので風水効果が欲しいという方にはダイモンジソウはあまり向いていないかもしれません。ダイモンジソウの育て方のポイント①:置き場所
それではいよいよダイモンジソウの育て方の解説をしていこうと思います。まず始めに紹介する育て方は『置き場所』についてです。置き場所は水やりと同じくらい重要な要素の1つですので気になる方は参考にしてくださいね。庭植えにすると根腐れを起こしやすい
庭植えは土の湿気によって根っこが腐る『根腐れ』が発生しやすいです。理由としては庭は雨が全く降らない期間が長くならない限りは乾燥することはなく、常に湿った状態です。常に湿った土は絶対根腐れを起こすわけではありませんが根腐れを起こしやすい環境になってしまうということです。根腐れを起こさないことは育て方ポイントにおいて重要な部分ですので注意してくださいね。庭植えするならロックガーデンがよい
どうしてもダイモンジソウを庭植えしたいと考えるのであれば『ロックガーデン』がおすすめです。ロックガーデンとは石を主体とし、水はけの良い土を組み合わせるガーデニングの方法です。ロックガーデンにすることで通気性や水はけが向上するので根腐れを防止することができます。 他にも高低差を活かしたガーデニングができるようになったり、上下のスペースを使うので多くの植物を育てることができるようになるなどメリットがたくさんありますよ。風通しの良い明るい日陰で育てる
ダイモンジソウを育てる時の配置場所は基本的に半日蔭、つまり風通しの良い明るい日陰に置くようにしましょう。真夏日に関しては直射日光に晒される場所に置いてしまうと葉焼けを起こしてしまい枯れてしまう恐れがあるので注意が必要です。また、風通しが悪いところに置いてしまっても湿度が高すぎて根腐れを起こす恐れもあるので注意が必要です。春~秋の場合:日にしっかり当てる
春、秋の季節はなるべく日光が当たる場所に置いてあげましょう。。半日くらい日に当てることが出来たらベストです。あまり気温が高い日は葉焼けを起こしてしまうので涼しい日にしっかりと日光を当ててあげることが大切です。夏の場合:直射日光を避けた涼しい半日陰~日陰に置く
夏の場合はとても暑い日が多いため、ダイモンジソウに限らず植物は直射日光を避けなければ葉焼けを起こして枯れてしまう恐れがあります。風通しの良い明るい日陰に置くことができればベストですよ。冬の場合:風が当たりすぎないよう注意する
冬での置き場所に関してですが、ダイモンジソウは耐寒性が高く、-10℃でも耐える事ができるので外に置いておいても問題ありません。軒下か室内に入れるようにしましょう。ただし、ダイモンジソウは乾燥を嫌う植物なので春の新しい芽が出てきたときに冷たい風を受けてしまうと新しい芽が傷んでしまうことがあります。冬の置き場所では風の当たらない場所を意識して置くようにしてくださいね。ダイモンジソウの育て方のポイント②:水やり
続いて水やりでのダイモンジソウの育て方をご紹介していきます。育て方において『水やり』は植物にとってとても大切な要素ですので十分理解しておくことが大切です。興味のある方はぜひご覧になってくださいね。土は常に湿り気をもたせる
タイモンジソウは乾燥を嫌う植物ですので土が常に湿っている環境を好みます。とはいえ水のやり過ぎは『根腐れ』を招いてしまうため、適度な湿度が重要となってきます。ヒタヒタになるまで水をあげるのではなく、土が少し湿った環境を維持できるように水やりをしましょう。春から秋は1日1回水をやる
春~秋はダイモンジソウの成長期です。成長期の間はかかさず毎日水やりを行い、新鮮な水を絶やさないようにしましょう。夏はすぐに水がなくなってしまうため土がカラカラにならないように注意してくださいね。夏の水やり:水切れに注意し、夕方根元にしっかり水をやる
先ほども少し触れましたが、夏の時期は気温が高く水分がなくなりやすいです。水切れを起こさないように夕方もう1度確認して土が完全に乾いていたら水やりをしましょう。 夏の水やりは涼しい早朝か夕方がおすすめです。暑い日中に水やりをしてしまうと蒸し風呂状態になってしまいダイモンジソウに良くありません。冬の水やり:土の表面が乾いているとき以外水やりは控える
冬の場合は土が完全に乾いているときだけで水やりは必要ありません。冬のダイモンジソウは休眠期に入るため、現状維持にしか水分を必要としないためです。そこに春~秋の成長期と同じペースで水やりをしてしまうと水分過多になり、『根腐れ』を起こしてしまうため水のやりすぎには注意しましょう。ダイモンジソウの育て方のポイント③:土
続いてご紹介させていただく育て方は土についてです。土選びも育て方に重要な要素の1つですので気にしていなかった方はぜひここで内容を確認してくださいね。水はけのよい土を用いる
観葉植物には様々な土がありますが、なるべく水はけのよい土を選ぶようにしましょう。水やりの見出しの時にも言いましたが、ダイモンジソウの水やりは冬以外では毎日行います。水はけの悪い土で毎日水やりをしてしまうとあっという間に根腐れを起こしてしまいますので注意してくださいね。市販の山野草用の用土や山砂でもよい
ダイモンジソウは山野草なので山野草用の用土を使用しても問題ありません。他にも安く購入できる山砂なども水はけの良いですのでダイモンジソウを育てることができますよ。ただし、山砂のみでなく他の土と配合もしなくてはいけませんので、自身の無い方は観葉植物用の土を購入することをおすすめしますよ。自作する場合は川砂7・赤玉土2・腐葉土1で混ぜ合わせる
観葉植物の土は慣れた方であれば自作する人も多くいます。ダイモンジソウのために自作したいのであれば川砂7・赤玉土2・腐葉土1を配合して作りましょう。こちらの配合は水はけに特化しており、毎日水をあげるようなダイモンジソウに適していますよ。ダイモンジソウの育て方のポイント④:肥料
次にご紹介する育て方は肥料についてです。肥料も分量やタイミングを誤ってしまえば植物にとっては害になりえます。ここでは肥料での育て方についてまとめましたのでぜひ参考に見ていってくださいね。ダイモンジソウはあまり肥料を必要としない
ダイモンジソウは肥料がなくてもしっかりと育ちますので、肥料をほとんど必要としません。反対に使いすぎると姿や形が乱れる恐れもありますので最低限、病害虫に負けないように強くするために与えるくらいで充分です。もし与えるのであればこのあとご紹介する、緩効性化成肥料をひとつまみか薄めの液肥にすることをおすすめします。植え付けの際に元肥として緩効性化成肥料を施す
もし肥料を与えたいのであれば植え付ける際に元肥として緩効性化成肥料をひとつまみだけ与えましょう。緩効性肥とは長い期間の間、ゆっくりと栄養を供給できる肥料です。期間は肥料によって様々ですが、約2~6か月間です。3月~9月の生育期に薄めの液肥を月1、2回程度施す
先ほど紹介した緩効性化成肥料を与えても良いですが、3~9月の成長期の間に付き1~2回のペースで草花用の液肥を1500~2000倍まで薄めたものを与える方法でも問題ありません。その方法について細かくご紹介していきますので気になる方は参考にしてくださいね。3月~5月は窒素主体のもの
肥料において窒素は植物の葉や茎の成長に1番大きく影響する栄養素です。窒素主体の肥料を選ぶことでダイモンジソウの葉や茎の成長を大きく促すことができます。6月以降はリン酸とカリウム主体のもの
リン酸には花つきや実つきをよくする効果があり、カリウムには根の発達を促進する効果があります。6月以降はある程度葉や茎が成長してくるのでリン酸とカリウム主体の肥料を使うことで9月の開花に向けて準備していきましょう。真夏の間はさらに薄めた肥料か無肥料がよい
真夏の場合は更に薄めて3000倍のもののほうがいいでしょう。小さいサイズであれば肥料はなしにしても問題ありません。肥料を与えすぎると草姿が乱れやすい
肥料を与えすぎると、栄養過多によって根っこにダメージを与えてしまいます。根っこが傷むと最終的に表に現れて草姿が乱れてきます。肥料焼けを起こしてしまった場合は見えない根っこが傷むので症状が現れた時には手遅れなことが多いです。なので肥料焼けは危険なので注意してくださいね。【成長したらすること】ダイモンジソウの植え替えについて
育て方が理解できたら次は植え替えについてです。ダイモンジソウに限らず観葉植物はある程度成長してきたら植え替えをする必要があります。 大きく育ってきたときに狭い鉢から植え替えをしなければ鉢内が根っこで埋め尽くされてしまう『根詰まり』が発生してしまいます。ここでは地植えと鉢植えの両方に分けて植え替えについてご紹介していきます。地植えの場合は株が増えたら数年に1回植え替える
地植えの場合は大きくなって子株が増えてきたタイミング、3~4年に1回に植え替えが好ましいです。植え替えの時期としては3月~4月の新しく芽が出てくる時期がいいでしょう。植え替え時に親株から子株から切り離して2~3株に分け、20cm程度間隔をあけて植えるようにしましょう。肥料を与えたいのであればこのタイミングに先ほど紹介した方法で行うようにしましょう。鉢植えの場合
続いて鉢植えで育てているダイモンジソウを植え替えたい場合についてです。地植えとはまた違ったポイントがありますので、気になる方はぜひみていってくださいね。年に1回、3月~4月上旬が適期
鉢植えで育てている場合は年に1回、3月~4月の時期に行いましょう。地植えとは違い鉢は狭いスペースです。大きくなってくると小まめに大きい鉢に移し替えしてあげる必要があります。これを怠ってしまうと鉢内が根っこで埋め尽くされてしまう『根詰まり』が発生してしまい、最終的には枯れてしまうことになるので年に1度の大きい鉢への植え替えを忘れないようにしましょう。一回りか二回り大きい鉢に植え替える
先ほども少し触れましたが『根詰まり』を防止するために一回りか二回り大きめの鉢に植え替えてあげましょう。狭い鉢のまま育成するとダイモンジソウによくありませんので注意してくださいね。古い土をよく落とし、傷んだ根を切り落とす
植え替えでもう1つ重要なことは根っこについて土を落とした後によく根っこを観察することです。黒くなった根っこは傷んでいるので剪定してしまいましょう。ここで傷んだ根っこを放置してしまうと、傷んでない根っこにも悪影響を与えてしまうので植え替えのタイミングついでに剪定してあげることが大切です。【成長したらすること】ダイモンジソウのお手入れについて
ダイモンジソウが成長してきたら、その時のお手入れも必要になってきます。そのままほったらかしにしていると、だんだんと元気がなくなることもありますので定期的なお手入れをする際のポイントをこちらでご紹介していきます。気になる方は見ていってくださいね。種を採らない場合は花が終わったら花茎を切る
ダイモンジソウは種を栽培しないのであれば花が枯れたら、花茎を切り落としてしまいましょう。枯れた部分を残しておくとダイモンジソウの元気な部分に悪い影響を与えてしまいます。この時に枯れた葉などがあれば一緒に切り落としてくださいね。 種を栽培したい方はもう少し待つと種が実ので切り落とさずに見守りましょう。葉が伸びすぎている・葉焼けした場合は8月頃に傷んだ葉を切る
伸びすぎた葉や、葉焼けした葉っぱなども8月ごろをタイミングとして全て切ってしまって問題ありません。8月ごろであればダイモンジソウはまだまだ葉を増やしていきますので、全体をいったん新しくするというイメージでキレイに剪定してしまいましょう。花の上を覆う葉や大きすぎてバランスの悪い葉も取る
花の植えを覆ってしまっている葉っぱや、大きさや姿かたちがバランスの悪い葉っぱも剪定してしまって問題ありません。とくに花と重なっている葉っぱなどは花に光が当たらず開花を邪魔する恐れがあるので入念に切り落としておきましょう。さらにダイモンジソウを増やす方法
ここからはさらにダイモンジソウを増やしていく方法についてまとめました。ダイモンジソウを増やす方法は大きく分けて2つ。ダイモンジソウを増やしたいとお考えの方は是非こちらの内容を参考にしてみてくださいね。株分け
まず1つ目にご紹介させていただくのは『株分け』。株分けとはある程度大きくなった植物を株ごと2~3等分に切り分けて別の鉢などで育てて増やしていく方法です。株分けのタイミングや方法をご紹介していきますので見ていってくださいね。植え替えの際に行う
基本的に株分けは植え替えのタイミング、つまり3~4月の間がいいでしょう。ダイモンジソウを鉢から取り出すと弱ってしまいますので頻繁に取り出すことはよくありません。そこで株分けも一緒に行ってしまうことで植物への負担を減らすことができますので、株分けは植え替えのタイミングがおすすめです。1/3~1/2程度に株を分ける
株分けは大きく成長したダイモンジソウを2,3等分に切り分けてください。切り分けたダイモンジソウは植え替えで説明した内容と同じ要領で、それぞれ鉢に入れて別々で育てるようにしてくださいね。殺菌剤などで傷まないように対策する
株分けするときに2~3等分に割るときに傷んでしまう可能性があります。不安な方は傷まないように株分け前に殺菌剤をかけて傷まないように対策してあげましょう。殺菌剤は病気の対策にもなりますので、株分け以外でも週に1回ペースであげるのもいいですよ。種まき
次に種まきによって増やしていく方法を解説していきます。種まきでのポイントをまとめましたので気になる方は是非みていってくださいね。花後に出たサヤから実ったタネをとり、乾燥させて保存
ダイモンジソウの種は花が終わった後に実るので、収穫したら乾燥させて保存してください。ここで乾燥させる理由としてはタネを湿った状態で植え付けてしまうとカビや病害虫、発芽率にも悪く影響してしまうため、植える前に乾燥させておくことが大切です。種まき前に湿らせた川砂などに混ぜて冷蔵庫の野菜室で保管する
ダイモンジソウの種子は完熟させて発芽させてから撒く必要があるため、乾燥させて保存していた種を種まき前に湿らせた川砂などにまぜて冷蔵庫の野菜室(0~5℃)で保管し発芽を促しましょう。翌春2月~3月頃、重ならないようにまく
管理してきたダイモンジソウの種子は2~3月ごろに、重ならないようにまいていきます。種をまき終わったら土が乾燥しないようにビニール袋を被せ、水を絶やさないようにしてください。その方法は次の見出しで具体的に解説してますので参考にしてくださいね。覆土はせずに底面給水で水やりをする
種をまいたら覆土はせずにビニール袋をかぶせて乾燥を防ぐようにしてください。種には上から水をかけるのではなく、下から水を吸い上げる底面給水という方法で水やりを行うことがポイントです。普通に水やりしてしまうと種が土の中に流されてしまい、病害の原因となってしまうため底面給水をするようにしましょう。発芽後、苗の大きさが1㎝を超えたら小さなポットに移す
無事、種子が発芽できて1cmを超えてきたら、小さいポットに移し替えてあげましょう。根がしっかりと大きく育ってきたら定植してあげてくださいね。ダイモンジソウによくあるトラブルと対処方法
ここではダイモンジソウを育てていく上でよくあるトラブルとその対処法についてご紹介しています。紹介している内容はどれも枯れる恐れのあるトラブルなので不安がある方はここで確認していってくださいね。病気
まず1つ目に紹介するトラブルは病気についてです。植物にも病気は存在し、ダイモンジソウも例外なく病気にかかりますのでここでご紹介しますね。灰色かび病
ダイモンジソウがよくかかる病気にあげられるのが『灰色かび病』。灰色かび病はカビによって引き起こされ、名前の通り灰色の粉が発生し、花や茎にシミが発生し、更に葉っぱは黒く変色してしまい焦げたような見た目になります。徐々に悪化していき最終的に花や実が腐ってしまいます。対処法:病変した葉は速やかに取り除く
病変してしまった葉や花などは見つけ次第すぐに切り落として取り除くようにしてください。放置しておくとそのまま病気が広がり、ダイモンジソウそのものが枯れてしまいますので定期的に見るようにしましょう。予防法:風通しの良い環境で育てる
白かび病の発生源は湿気によって発生してしまう『カビ』であるため、風通しの良いところでダイモンジソウを育ててあげればカビは発生しませんので、白かび病のリスクを低下させることができますよ。害虫
続いてダイモンジソウに見られる他のトラブルとしてあげられるのが『害虫』です。こちらは観葉植物全般に言えることで、ダイモンジソウも例外ではありません。数いる害虫の種類の中でもダイモンジソウによくみられる害虫を紹介させていただきます。ヨトウムシ
ヨトウムシはヨトウガの幼虫で、主に夜中に行動しています。ヨトウムシはダイモンジソウの葉っぱを食べてしまいますので、もし葉っぱをチェックしたときに食べられた形跡があるときはヨトウムシの食害に遭った可能性が高いです。アブラムシ
アブラムシは植物の汁を吸ってしまうため、栄養が奪われてしまい枯れる恐れがでてきます。さらにはアブラムシの排泄物によって『すす病』にかかってしまうと光合成の効率が低下してしまうためダイモンジソウの健康を損ねてしまう恐れがあります。対処法:見つけたら捕殺するか、殺虫剤をまく
害虫は見つけ次第、捕殺するか殺虫剤を撒きます。ヨトウムシなどの夜行性の虫などは捕殺することは難しいため、観葉植物用の殺虫剤などを使って防虫対策するようにしましょう。ダイモンジソウの冬越しのしかた
ここからはダイモンジソウの冬越し方法について解説していきます。ダイモンジソウは冬は休眠期になるため春~秋の間とは管理方法が異なります。冬の管理を怠ってしまうと春に元気なダイモンジソウを見ることができなくなってしまうのでぜひご覧になってくださいね。ダイモンジソウは寒さに強い
先ほど育て方の際にも触れましたが、ダイモンジソウは非常に寒さに強く―10℃まで耐えることができます。そのため、冬場でもダイモンジソウは外に置いて冬越しすることも可能な植物です。ただし、ダイモンジソウは乾燥を嫌うため、外で冬越しさせる場合は風の当たらない軒下などに置いてあげるようにしましょう。北風と乾燥に気を付ける
先ほども少し触れましたが、ダイモンジソウは寒さには強くても乾燥には弱いです。乾燥させたまま春を向かえてしまうと新しい芽が出てこなくなる恐れありますので、外で冬越しさせたいのであれば、風の当たらない家の軒下などで管理してあげましょう。落葉期に茶色くなりかけた葉はすべて取り除く
落葉期に茶色くなりかけた葉っぱは全て切り落として取り除いてあげましょう。そのまま残しておくと、そこから腐り傷んでくる恐れがありますので防止するためにも確認して剪定しておきましょう。凍結に注意する
ダイモンジソウは氷点下でも耐える事が出来ますが、水やりを行った際に水が凍ってしまいダイモンジソウを凍らせてしまうことがありますので、もし凍結してしまう恐れがあるのであれば置き場所を変えてあげましょう。ダイモンジソウの夏の管理のしかた
春~秋の成長期の中でも夏が一番過酷な時期です。夏の管理を怠ると枯れてしまう恐れもあるのでここでは夏の管理の方法に焦点を当ててご紹介していきますね。暑さと乾燥から保護する
ダイモンジソウは寒さには強いですが暑さには弱い植物です。さらに乾燥にも弱いため、暑い夏の時期はどちらの対策も怠らないようにしてあげることが大切です。対策についてご紹介しますので参考にしてくださいね。二重鉢にする
気温が高い夏の時期は鉢内の用土の水分が蒸発しやすく、すぐに乾燥してしまいます。それを防ぐために取れる対策が二重鉢で育てる事。夏の間は二重鉢にしておくことで用土の乾燥を防ぐことができます。砂床に置く
砂床にダイモンジソウを置くのも暑さと乾燥対策になりますので、砂床を作れる方はこちらもおすすめですよ。遮光ネットや遮光シートで直射日光を遮る
ダイモンジソウに限らず、観葉植物全般に言える事ですが、直射日光にあててしまうと葉焼けしてしまい枯れてしまうおそれがありますので風通しのいい半日蔭で管理してあげましょう。日光がどうしても当たってしまう場合は遮光ネットや遮光シートを使って日光をある程度遮ってあげましょう。よしずやすのこで風通しを良くするのもおすすめ
ダイモンジソウは乾燥を嫌いますが、反対に湿気が溜まりすぎるのも問題です。風通しの良い空間があまりないのであれば、よしずやすのこを使って風の通り道を作り、風通しを良くすることもおすすめです。ダイモンジソウを盆栽にする場合
ここではダイモンジソウを盆栽にしたいと考えている方に向けて内容をまとめました。盆栽に育てる上でのポイントを解説していますので興味のある方はご覧になってくださいね。石づきで育てる方法
石そのものに根っこを絡ませ、自然の風景を本格的に再現する石づき盆栽。その作り方をいくつかの要点に分けて解説していきますね。ケト土をよく練ったものを厚さ0.5~1cmに塗る
石づき盆栽の石にケト土を良く練ったものを厚さ0.5~1cmで塗っていきます。ケト土は水持ちがよく保水性に優れているほか石に植物を接着する役割ももっているため石づき盆栽を作る際には必要となります。その上に根と根茎を広げて植える
石にケト土を塗り終わったらその上にネト根茎を広げて石に張り付けながら植え付けていきます。表面に苔を張って木綿糸などで固定する
ダイモンジソウを石に張り付けることができたら、次は表面に苔を貼って木綿糸などを使って固定しましょう。苔を貼ることで水やりをした際に、水がすぐ流れ落ちてくれるのでダイモンジソウにはピッタリの環境になりますよ。自生場所は湿り気のある岩の上
ダイモンジソウの自生場所は草原や山ではなく、湿り気のある岩の上であるため、盆栽で育てるということはダイモンジソウを自生姿で育てることができ、ダイモンジソウのありのままの姿で育てることができるのでおすすめですよ。ダイモンジソウの育て方を紹介!時期ごとのケア方法やよくあるトラブルまでのまとめ
ここまでダイモンジソウの育て方についてご紹介してきましたが、いかがだったでしょうか?ダイモンジソウは多年草で毎年秋ごろに素敵な花を咲かせてくれますので、育て方に注意して育ててくださいね。本記事の内容をまとめますと以下の通り。- ダイモンジソウには『自由』を始めとしたいい花言葉が多い
- ダイモンジソウは風通しのいい半日蔭に置く
- ダイモンジソウは春~秋は毎日、冬は土が乾いたら水やりをする
- ダイモンジソウの土は水はけの良い土を使うとよい
- ダイモンジソウに肥料はほとんど必要なく少しで充分
- ダイモンジソウはある程度成長すると増やすことができる