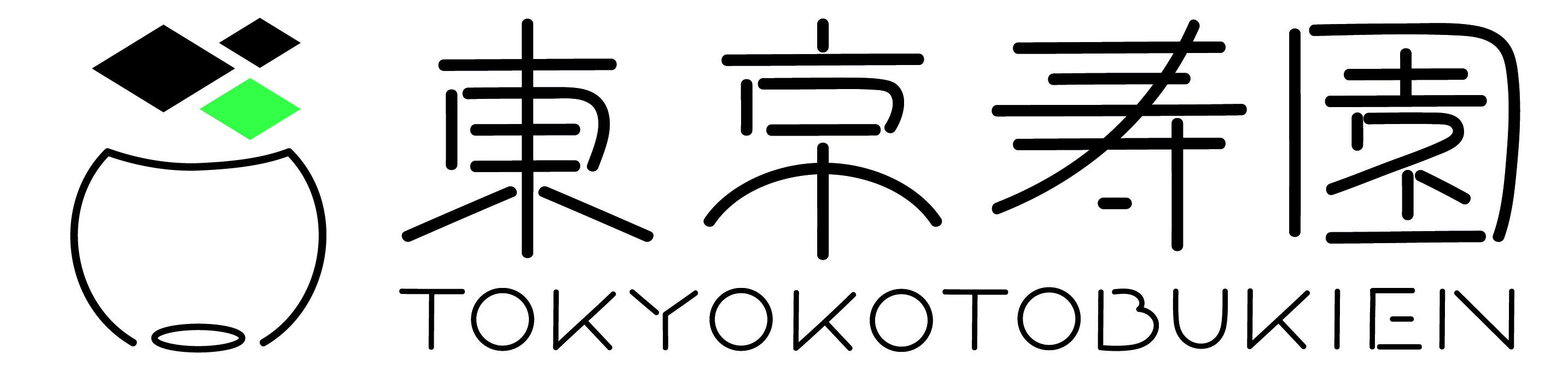目次
ぷっくりとした見た目の可愛い多肉植物。サボテンをはじめとして、数多く品種のある人気ある植物です。多肉植物の育て方においては非常にシンプルで、水やりを特に意識していれば、基本的には丈夫な品種です。
この記事では多肉植物の基本情報から元気に成長する育て方、増やし方まで以下の流れで解説していきます。
- 基本的な多肉植物の情報を解説
- 多肉植物の基本的な育て方①置き場所②水やり③土④肥料⑤植え替えを解説
- 多肉植物の増やし方はどうやるのか
- 多肉植物に起こりやすいトラブルと対処法をご紹介
- 雪国でも多肉植物は育てられるのか
- 多肉植物のカット苗の購入後にすることまとめ
- 多肉植物の寄せ植えについて
- 多肉植物のおすすめの種類
- まとめ
そもそも多肉植物とは?
それではまずは、そもそも多肉植物とはなんなのかについてお話ししていくところから始めましょう。まだあまり詳しくない初心者さんはぜひ聞いてみてくださいね。アフリカなど乾燥した地域が原産の植物
多肉植物は、アフリカなど乾燥した地域が原産の植物です。そのため、元からアフリカなど乾燥した環境でも生きていけるほど、かなり丈夫な種類の植物でもあります。体に水分をたくわえる性質をもつ
ぷっくりとしたその見た目は、実はアフリカなど極度に乾燥した地域でも生きていけるように、体に水分をたくわえる性質を持っています。ぷっくりとした姿やとげとげした姿など独特な見た目
多肉植物は、体に水分をたくわえる性質を持っているため見た目はとてもチャーミング。ぷっくりとした姿やとげとげした姿に魅了されたファンも多い人気の植物で、独特の雰囲気を醸し出すインテリアにもよく似合います。初心者でも手入れが楽で育てやすい
先ほどもお話ししたように多肉植物は、乾燥した環境でも生きていけるほど、かなり丈夫な種類の植物ですので室内栽培にも向いています。特に初心者さんには手入れが楽で育てやすいというメリットがありますよ。100均などでも手に入る
また、なんと言っても多くの多肉植物は、実は100均などでも手に入る相当なコストパフォーマンスの優れている植物でもあります。初めて育てる方はぜひ100均などのお安いお店で購入して育ててみるのはいかがでしょうか。エケベリアなども安く売っていることもありますよ。生育する季節によって種類が分けられる
また、多肉植物の特徴として、生育する季節によって種類が分けられる「型」というものが以下のように存在します。分類すると3つありますよ。春秋型
春秋型は、春と秋に生育期を迎える多肉植物のことを指します。春と秋は日当たりの良い場所に置き、冬は室内に移動させて寒さをしのぎます。夏場は水を断水して根腐れを防ぎます。春秋型には、エケベリア・セダムなどがあります。夏型
夏型は、夏に生育期を迎える多肉植物のことを指します。夏は直射日光を避けた日当たりの良い場所でよく育ちます。冬は必ず室内で管理し、エアコンなどの風が当たらない場所がおすすめ。冬型
冬型は、冬に生育期を迎える多肉植物のことを指します。冬型は冬に生育期を迎えるため、冬場にこそしっかりと日光を当てて、夏型とは反対に夏場は完全に断水させる必要がある植物です。多肉植物の基本的な育て方①置き場所
さて、まずは多肉植物の基本的な育て方の中でも肝心な、置き場所について解説していきます。生育する季節によって種類が分けられる「型」に合わせて置き場所は変わってきますよ。春秋型
まずは春秋型の置き場所についてみていきましょう。春と秋:風通しと日当たりのよい場所に置く
春秋型の春と秋は、風通しと日当たりのよい場所に置くようにするとよく育ちます。この時期が生育期のため、風通しと日当たりのよい場所に置くことでより成長がしやすくなります。夏:風通しのよい半日陰に置く
夏は、風通しのよい半日陰に置きましょう。温度が上がることや、直射日光のパワーが強まることからも、半日陰がおすすめ。冬:室内や温室で管理する
冬は、室内や温室で管理をしましょう。冬場は温度管理が最も多肉植物の生育に影響するので、特に注意を払って管理するように心がけましょう。夏型
続いては夏型の置き場所について解説していきます。1年中日当たりのよい場所を好む
夏型の多肉植物は、1年中日当たりのよい場所を好みます。そのため、基本的には他の季節の型の多肉植物よりも比較的丈夫であることが多いです。春~秋:風通しの良い日向
また春~秋は、風通しの良い日向で栽培することがおすすめ。乾燥させすぎるのも良くないので、適度な風通しの良い日向を選びましょう。冬:日当たりのよい室内や温室
また冬は、日当たりのよい室内や温室がいいでしょう。基本的に冬は、どの季節の型も屋外での栽培をやめ、室内に移動させるのがいいでしょう。冬型
最後は冬型の多肉植物をみていきましょう。春~夏:風通しの良い半日陰
冬型の多肉植物は、春~夏は風通しの良い半日陰に置くことを推奨しています。しかし本格的な夏になってきたら休眠期に入るので、特に涼しい場所に移動させるようにしましょう。冬:日当たりの良い室内
冬型はまさに冬場に生育期を迎えるため、日当たりの良い室内で栽培することでよく成長します。他の季節の型の植物と異なるので不安な方も多いでしょうが、しっかりと日光を当ててあげましょう。種類によっては屋外を好むものもある
しかし中には例外のある多肉植物もいます。基本的には多肉植物は室内で栽培しますが、種類によっては屋外を好むものもあります。もしかするとあなたが育てたい多肉植物がその場合もあるので、よく調べてみるのもおすすめです。多肉植物の基本的な育て方②水やり
続いては多肉植物の基本的な育て方の水やりについてお話ししていきます。こちらも、置き場所同様に、季節の型によって水やりの方法も異なってきますよ。春秋型
まずは、春秋型の水やりについてお話ししていきます。春と秋:土の表面が乾いたら
春と秋は、土の表面が乾いたらしっかりと水やりをしましょう。表面が乾いたのを確認してから水やりをするというのが肝心です。夏:1カ月に3~4回が目安
夏は、1ヶ月に3~4回が目安になります。おおよそ週に一回が目安になりますので、ぜひ参考に水やりをしてみてください。冬:1ヶ月に1~2回
冬は、1ヶ月に1~2回が目安になります。春秋型の水やりは、特に冬は断水気味でOKです。水のやりすぎはNGなので覚えておきましょう。夏型
続いては夏型の水やりについてみていきましょう。生育期の5~9月頃:土の表面が乾いたら
夏型の水やりは、生育期の5~9月頃に土の表面が乾いたら水やりをしましょう。この生育期に合わせてしっかりと水やりをするのが重要です。冬:休眠期のため断水する
冬は休眠期のため断水しましょう。非常に簡単で手間がかからないので、楽な時期でもあります。冬型
最後は冬型の水やりについて解説していきます。生育期の11~4月頃:土の表面が乾いたら
冬型は、生育期の11~4月頃に、土の表面が乾いたら水やりをしましょう。他の季節の型の水やりと正反対なので、少し不安がある方もいるかもしれませんが、これが通常ですので覚えておきましょう。夏:断水するか、乾燥気味に育てる
また、夏は断水するか、乾燥気味に育てることで、休眠期に根腐れや根詰まりにならないですみます。覚えておきましょう。多肉植物の基本的な育て方③土
続いては多肉植物の基本的な育て方の土について解説していきます。特に土は植え替えてからはずっとそのままのものなので、非常に土選びは重要です。水はけのよい土が適している
多肉植物の土は、水はけのよい土が適しています。水はけの良い土を使用することで、排水性が高まり、うまく土の中の保水状態をコントロールしてくれます。多肉植物用の土を使うのがおすすめ
とは言ったものの、「どれが水はけの良い土なのかわからない」という方は、多肉植物用の土を使うのがおすすめです。これは初心者さんには特に簡単なので、まずは多肉植物用の土を使うことから始めてみるのも良いでしょう。観葉植物用の土でも代用できる
またこれはよくある質問ですが、「観葉植物用の土でも代用できるのか」というと、実は代用できます。多肉植物用の土ではなく、観葉植物用の土でも育てることはできますが、おすすめなのはやはり多肉植物用の土にはなります。園芸用土を使う場合
また、園芸用土を使う場合は、以下のような配合の土を使うのがおすすめです。園芸用土3:赤玉小粒4:軽石3 の割合で混ぜる
園芸用土を使う場合は、園芸用土3:赤玉小粒4:軽石3の割合で混ぜると良いでしょう。うまく排水性も高まり、土壌環境も非常に良いです。くん炭、川砂、鹿沼土小粒やヤシの繊維を混ぜてもよい
また、くん炭、川砂、鹿沼土小粒やヤシの繊維を混ぜるのもおすすめです。これらを使うことで、排水性・保水性を高め、無菌なので清潔に管理することができますよ。上級者さんにはおすすめです。多肉植物の基本的な育て方④肥料
続いては多肉植物の肥料について解説していきます。どのような時に必要なのか、またどんなことに注意するといいのかについてお話ししていきます。植え替えの際に緩効性肥料を土に混ぜる
多肉植物は、植え替えの際に緩効性肥料を土に混ぜることで、数ヶ月の期間ゆっくりと成長に合わせて効いてくる上に、何度も肥料を与えなくて済むので一石二鳥のメリットもあります。1年以上植え替えない場合は生育期に液肥を薄めて与える
また、1年以上植え替えない場合は生育期に液肥を薄めて与えることがおすすめです。液肥は即効性があるため、その期間の生育期によく効き、成長を促進してくれます。肥料の与えすぎに注意する
しかし、肥料は与えるだけ良く育つというわけではなく、与えすぎると肥料焼けを起こし根腐れや根詰まりといった二次的な被害にもつながるので、注意してください。多肉植物の基本的な育て方⑤植え替え
最後は植え替えについてお話ししていきます。植え替えをするタイミング、時期、植え替えに必要なものなどをここからは解説していきます。始めて植え替えをする方は是非参考にしながら植え替えてみてくださいね。植え替えのタイミング:1〜2年に1回が目安
多肉植物の植え替えのタイミングは、1〜2年に1回が目安になります。基本的に多肉植物は他の観葉植物などと違って成長が緩やかなので、そこまで頻繁な植え替えを必要としませんが、土の状態の悪化や鉢の中の根っこの成長はあるため、上記の頻度がおすすめ。植え替えの時期
続いては多肉植物の植え替えの時期がいつなのかについて解説していきます。成長期に入る少し前がよい
季節の型の種類によって時期は変わりますが、共通して言えることは、成長期に入る少し前がおすすめです。これをあなたが育てている多肉植物の季節の型に合わせて時期を考え植え替えをしてみてください。真夏や梅雨時、寒い冬は避ける
また注意するべきことは、真夏や梅雨時、寒い冬は避けるようにしてください。これはどの季節の型の多肉植物でも同様です。植え替えに必要なもの
続いては多肉植物の植え替えに必要なものを見ていきましょう。鉢
まず鉢は植え替えに必ず必要です。今よりも一回りだけ大きめの鉢を選ぶことがおすすめです。土
土は先ほども解説した通り、排水性の高い土か、多肉植物専用の土を購入して用意しておきましょう。鉢底石
鉢底石はまさに鉢の底に敷く石で、排水性を高めてくれる役割を持っています。割りばしorピンセット
割りばしやピンセットがあると、細かい作業ができることや、土を奥まで入れることにも役立ちます。スコップ
スコップは土を鉢に入れるときに手が汚れないためや、周りを汚さないためにも役立ちます。鉢底ネット
鉢底ネットは排水性を高めることもありますが、土が鉢の穴から流れ出ないようにするために必要な道具でもあるのであると非常に便利です。植え替えのしかた
続いては植え替えの方法について解説していきます。順番でお話ししていくので、初めての方はこの通りやってみるのもおすすめです。①鉢に土を入れる
まず鉢に土を入れましょう。この時、入れすぎないように、2/3程度に土を入れましょう。②苗を抜く
現在の古い鉢から多肉植物の苗を優しく引き抜きます。根っこや苗に傷をつけないように丁寧に作業を行いましょう。③根を整える
また、根は伸びすぎているものや、元気のない余計な根は切り取って、整えていきましょう。④鉢に移して土を入れる
最後に、根を整えた苗を鉢に移して残りの土を入れて完成です。多肉植物の増やし方
続いては、多肉植物の増やし方についてお話ししていきます。どんな増やし方があるのか知りたい方、多肉植物を増やしたい方はぜひ参考にしてください。葉挿し
まず葉挿しというやり方で多肉植物を増やすことができます。葉を切り取って土に挿し、根を生えさせる方法
葉挿しは葉を切り取って土に挿し、根を生えさせる方法のことを言います。葉っぱは自然に落ちたものでも、葉挿しようにもぎ取っても大丈夫です。葉挿しのやり方
- 葉挿しする葉っぱを用意します。
- 土を用意しますが、この時土の粒子は発根しやすくするために細かいのがおすすめです。
- 葉の先端を少しだけ土に埋めて置きます。発根するまでは水やりはしません。
挿し木
続いての増やし方は挿し木です。茎を切り取って乾燥させ、根を出させる方法
挿し木は茎を切り取って乾燥させ、根を出させる方法のことを言います。剪定時に出た茎を使用してもOKです。挿し木のやり方
- 挿し木用の茎を用意します。この時、茎についている葉っぱは切り取るようにしましょう。
- 数日間茎の切り口を乾燥させる準備をしましょう。
- その後、用意した土に挿して発根するまで気長に待ちましょう。十日前後が経ってから、水やりをしましょう。
株分け
最後は株分けという増やし方をご紹介していきます。根から分離させて育てる方法
株分けは、根から分離させて育てる方法のことを言います。根を分けるイメージです。大きめの多肉植物でおすすめの増やし方になり、小さいサイズの株ではおすすめできない増やし方です。株分けのやり方
- 水はけの良い土を用意します。
- 株分けを行うために今の株を分離させます。
- 親株と子株に分けていき、子株を新しい鉢に植え替えます。
- 植え替え後、1週間ほどしたら水やりをして完成です。
夏型の多肉植物は冬場に挿し木や株分けを行わない
夏型の植物も春秋型と同様に冬場は室内や温室での管理がおすすめ。また冬場に挿し木や株分けなどを行うと失敗するので行わないようにしましょう。 しかし、夏型の多肉植物は冬場に挿し木や株分けを行うと、失敗しやすくなってしまいます。というのも、夏型の多肉植物は冬は休眠期なので、挿し木や株分けといった株に影響を与えやすい作業を行うと回復しきれず失敗しやすくなってしまうので、注意してください。多肉植物に起こりやすいトラブルと対処法
お次は、多肉植物に起こりやすいトラブルの原因と対処法について解説していきます。事前に多肉植物に起こりやすいトラブルと対処法について知っておけば、未然にそういった事態を防ぐことができますよ。病気
多肉植物も気をつけていないと病気になってしまうこともありますよ。以下の病気には特に注意してください。原因と対処法を見ていきましょう。根腐病:高温多湿・休眠期での水やりを避ける
高温多湿な環境や、休眠期に水をたくさんやると、根が腐ってしまうことがあります。土が乾いてから水やりし、過度な水を避けましょう。排水性・通気性の良い土を使うことも大切です。黒斑病:対処法はないため綺麗な葉が生えるのを待つ
黒斑病の特効薬はないため、感染した部分を切り取り、健康な葉が成長するのを待つしかありません。感染拡大を防ぐため、他の植物との接触を避け、早めの対処が重要です。害虫
続いては害虫による被害を見ていきましょう。以下のように対処することがポイントです。ハダニ:水で10倍に薄めたお酢を直接吹きかける
ハダニは赤褐色の小さな虫です。特にハダニは葉の裏側に発生し吸汁する害虫で、お酢を水で薄めたものをスプレーして退治できますが、葉に直接かけすぎないよう注意をして行いましょう。アブラムシ:テープなどを使って取り除くか、水で洗い流す
アブラムシは葉や茎に付いて吸汁し、成長を妨げる害虫です。テープで取るか、水で優しく洗い流す方法が効果的です。他の植物にも広がらないよう、早めに対処しましょう。カイガラムシ:ピンセットで除去するか、歯ブラシなどでこすり落とす
カイガラムシは強力な害虫です。カイガラムシは殺虫剤などでは死滅しないので、アナログな方法ではありますが、ピンセットで取ったり、歯ブラシでこすって除去することがおすすめです。植物全体をチェックして根気よく対処しましょう。雪国でも多肉植物は育てられる?
続いては、「雪国でも多肉植物は育てられる?」というよくある疑問について解説していきたいと思います。北海道のような寒い雪国では室内で越冬する
結論からお伝えすると、北海道のような寒い雪国では、多肉植物を室内で越冬させるのが一般的です。寒さに弱い多肉植物は、室内の暖かい環境で生き延びることができます。締め切った風通しの悪い部屋ではカビることもあるため注意
しかし、締め切った風通しの悪い部屋では湿度が高まり、カビの発生が懸念されます。こまめな換気と適切な水やりを心掛けて越冬させてください。徒長や変色などの危険がある
また、寒い環境下では多肉植物が徒長(間伸びする)してしまったり、葉の色が変わる変色の危険があります。冬場も適切な日光と、温度管理を行い、成長をサポートしましょう。小屋・ハウスで越冬する場合は暖房設備が必須
もし小屋やハウスで越冬する場合は、暖房設備が必須です。寒さから植物を守り、健康な状態を維持するために、適切な温度を維持することが重要です。多肉植物の種類によって適切な温度範囲が異なるため、その点も考慮することもず重要なポイントになります。多肉植物のカット苗の購入後にすること
続いては、多肉植物のカット苗の購入後にすることをお話ししていきます。カット苗は、根っこを切り落とした挿し木用の苗のことを言います。カット苗の状態チェックをする
まずはカット苗を購入したら、カット苗の状態をチェックしましょう。チェックするべきポイントは以下になります。害虫や病気がないか
まず害虫や病気がないかチェックしましょう。植える前に特に大事なのはこの害虫や病気がないかということ。成長に大きく関わるのでよく見て確認することが大事です。名前を調べる
続いては名前を調べることです。名前を調べることで、正確にどんな育て方や植え方かがよくわかります。枯れ葉や古い根を取り除く
また、枯れ葉や古い根を取り除くことも重要です。枯れ葉や古い根があるまま植えてしまうと、土の中で腐ってしまうこともあるので、必ず植え替える前には取り除いてください。植え付ける
お次は植え付けるにはどうすればいいのかをお話ししていきます。すぐに植え付ける
カット苗を購入したら、すぐに植え付けるようにしましょう。すぐ植えるべきな品種の多肉植物は、セダムやハオルシアなど。切り口を乾かしてから植えるものもある
また、カット苗は乾燥している状態でないと植えることができないため、切り口を乾かすのに数日間要してから植えるものもあるからこそ、しっかりとカット苗の名前を調べることが重要になってきます。水やりを始める
そうして土に挿し、根が土に安定してきたのを確認できれば、水やりを始めましょう。少量ずつ水やりをすることで、根っこの安定性を壊さないようにすることができます。多肉植物の寄せ植え
続いては、多肉植物の寄せ植えについて解説していきます。多肉植物はサイズの小さいものから大きなものまでありますが、どれも非常に寄せ植えに向いていますよ。ここからはどのように寄せ植えをすると良いのかを解説していきます。寄せ植えのイメージ
寄せ植えは、花壇や大きめの鉢に多肉植物を複数植えておしゃれに飾ることを言います。どのようなことを意識して寄せ植えをするとより可愛くできるのかをみていきましょう。色にこだわる
まずは色に意識を向けてみることがおすすめ。多肉植物はさまざまな色がありますが、その中でも同系色にまとめてみると「統一感」が出ておしゃれに見えやすくなります。鉢植えにこだわる
また、鉢植えにこだわることで、「どこに置いて楽しむのか」に合わせた寄せ植えもできますよ。例えば棚に置くのであれば、そこまで大きすぎないサイズの鉢がいいでしょう。飾り方にこだわる
最後は飾り方にこだわることでも寄せ植えを楽しめますよ。例えばハンギングができるように寄せ植えをすればお気に入りの場所に飾ることもできるので、「どんな飾り方にしたいか」に合わせるのも楽しいですよ。寄せ植えの作り方
- 寄せ植えに使用したい多肉植物の苗を準備します。
- 寄せ植えしたいお好きな鉢や花壇を決め、「完成形をイメージしながら」植えていきます。
- イメージよりも大きい場合には剪定をしながら、少しずつ植えていきます。
- 最後まで植えることができて満足いけば、完成になります。
多肉植物の種類
最後は、多肉植物の中でもおすすめの種類についてご紹介していきます。5種類に厳選してまとめてみたのでぜひお気に入りの多肉植物を探す参考にしてみてくださいね。桜吹雪:紅葉斑の珍しい品種
1つ目は桜吹雪です。桜吹雪は紅葉斑の珍しい品種で、本当にまるでサクラのように綺麗なピンク色をしており、お部屋の中に置いてもよく目立つ可愛い印象の多肉植物です。黒法師:暑さが苦手な品種
2つ目は、黒法師です。黒法師も名前の通り黒い葉を持つ珍しい多肉植物です。暑さが苦手な品種なので、半日陰で育てるのがおすすめ。背の高さがあるので、インパクトのある多肉植物でもあります。モニラリア:うさぎの耳のような葉が特徴
3つ目はモニラリアです。モニラリアはうさぎの耳のような葉が特徴な多肉植物です。本当にうさぎの耳のように見える葉は、可愛すぎるのでファンの多い多肉植物でもあります。ヘラクレス(七福神):葉がバラのようなロゼット状になる
4つ目はヘラクレス(七福神)です。ヘラクレス(七福神)は、葉がバラのようなロゼット状になる多肉植物でもあります。バラの花がパッと開いているかのように見えるので、非常に可愛らしい印象のものでもあります。白雪姫:葉が薄いピンクに色づく
5つ目は、白雪姫です。白雪姫は葉が薄いピンクに色づく多肉植物です。先ほどのヘラクレスにも似ていますが、色が若干薄いピンクになるのが白雪姫の特徴です。おしゃれな鉢との相性も良さそうな多肉植物になります。【まとめ】多肉植物の育て方を解説!初心者向けのケアからトラブルの対処法まで
いかがだったでしょうか?多肉植物の育て方から増やし方、寄せ植えなどの楽しみ方まで丸っとご理解いただけたのではないでしょうか。 今回の記事のポイントは以下になります。- そもそも多肉植物はアフリカなど乾燥した地域が原産で、体に水分をたくわえる性質のある独特な見た目の植物
- 生育する季節によって種類が分けられ、春秋型・夏型・冬型がある
- 置き場所・水やりは、春秋型・夏型・冬型に分けて変化をさせながら育てることが重要
- 多肉植物には水はけのよい土が適している多肉植物の肥料は、植え替えの際に緩効性肥料を土に混ぜ、場合によっては液肥も与える
- 植え替えのタイミングは1〜2年に1回が目安
- 多肉植物の増やし方は、葉挿し・挿し木・株分けがある
- 多肉植物は根腐病や黒斑病になりやすいため、高温多湿・休眠期での水やりを避けるよう心がける
- 北海道のような寒い雪国では室内で越冬し、とにかく温度管理を徹底する
- 多肉植物のカット苗の購入後にすることは、枯れ葉や古い根を取り除き、すぐに植え付けるか切り口を乾かしてから植える
- 多肉植物の寄せ植えは、色や飾り方にこだわるとおしゃれにできる