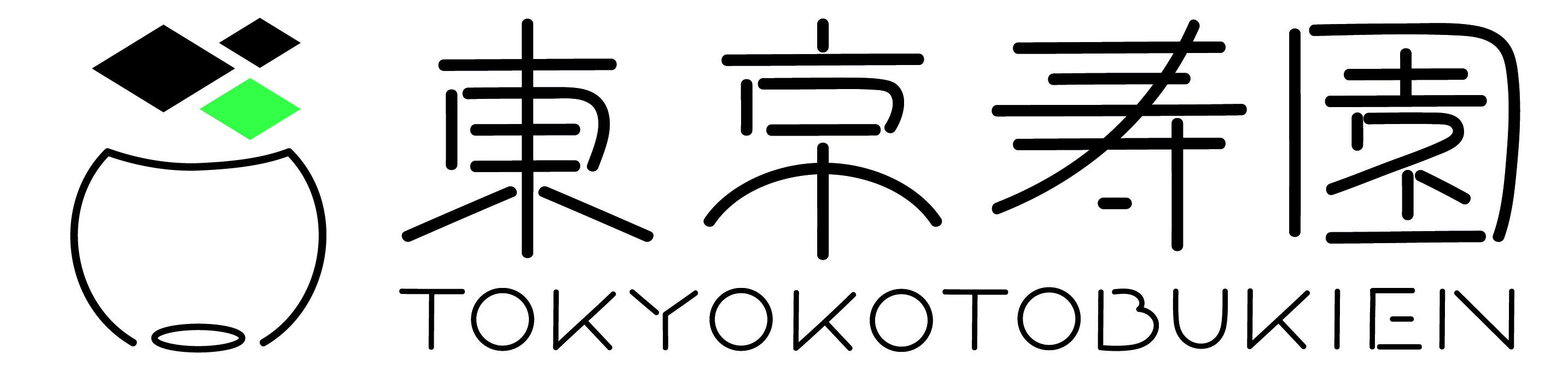目次
インテリアとしておしゃれな観葉植物。見てるだけでとっても癒されますよね。コロナ禍でおうち時間が増えた昨今、その人気はますます高まっているようです。
そんな観葉植物に、白い異物や黒い粒が目に付くようになった事はありませんか?パッと見、ゴミかホコリのように見えるかも知れませんが、実はこれ「害虫」なんです。
害虫は見た目が気持ちが悪いし、生育の妨げにもなるので、早く駆除しなければなりません。でも、どうやって駆除して良いのか、どんな対策があるのかもよく分かりませんよね。
何度か害虫の被害にあったことがある方はお気付きでしょうが、よくよく観察すると、見た目の違いから、害虫にも色々種類があることに気づきます。
そう、害虫には、白いもの、貝のようなもの、うねうねしたものなど、幾つか種類があり、その退治方法、予防方法もそれぞれバラバラなんです。
そもそも、害虫がつかない生育方法があるのなら、それに越した事はないって思う方もおられるかもしれません。
このように、害虫の種類について詳しく知れば、それについての対策も具体的になっていきます。すべての害虫に殺虫剤が効けばいいですが、イマイチ効果がない虫もいるかもしれませんし、その特徴や使い分けのポイントを抑えることも大事です。
そこでこの記事では、
- 観葉植物に付く白い虫の正体、その生態や特徴
- 害虫の種類ごとの退治方法と、その際気をつけなければいけない重要ポイント
- 殺虫剤の種類、オススメ商品、その使い分け
- 虫がつかないようにする事前の予防策
- 虫がつかない観葉植物の生育方法(ハイドロカルチャー)
をご紹介します。
この記事をご覧になれば、あなたのカワイイ観葉植物を白い虫から守る術を学ぶことができます!!
また、簡単なQ &Aも記載してますので、記事をお読みになった上での素朴な疑問にもお答えできるかと思います。
是非、最後までご覧ください!!
観葉植物に付く白い虫の種類
ここでは、観葉植物に付く虫にはどのようなものがいるのか具体的に見ていきましょう。白い虫、貝殻、うねうね、形態はバラバラですが、そういった害虫たちの生態を知ることで、今後の対策にもつながっていきます。貝殻のようなものが付着している:【カイガラムシ】
「カイガラムシ」は植物や樹木にベッタリと密生し、栄養を吸い取って生活する寄生虫の一種です。 5~7月の繁殖期をピークに発生しますが、温かい室内にある観葉植物などの場合は、通年を通して発生する可能性があります。年柄年中すがたを見せるカイガラムシですが、その生命力は大変強く、そのため、寄生先に選ぶ植物の種類も広範囲に及びます。貝殻のような形のもの、白いふわふわしたもの、その形状や生態には細かい分類があり、名前もさまざまですが、総称して「カイガラムシ」と呼んでいます。
貝殻状の殻をもったカイガラムシの代表格として、- 「タマカタカイガラムシ」
- 「ヒラタカタカイガラムシ」
- 「コナカイガラムシ」です。
これらのカイガラムシ全般に共通する特徴は、口から出す細い針で、寄生先の植物の茎や樹木の幹を突き刺し、その養分を吸い取ることです。カイガラムシに栄養を吸われた植物は衰弱していき、さらに被害が進むと葉や枝が枯れる事もあるので、出来るだけ早い駆除が必要となります。
カイガラムシの多くは、硬い殻を背負っていて、その殻の中に、余った養分と排泄物を蓄えています。カイガラムシの蓄えた排泄物は、糖分を豊富に含むため、「カビ」の栄養源になります。カビが栄養を求めて植物に付着し、その葉を覆うと、いわゆる「すす病」と呼ばれる病気を引き起こします。すす病にかかった植物は、光合成が出来なくなり元気がなくなって、最終的には枯れてしまう恐れもあります。また、虫の排泄物にコバエやアブラムシといった別の虫がたかる事も。つまり、カイガラムシは害虫としてだけでなく、そのほかの病気や虫を誘引する触媒でもあるという事です。 また、カイガラムシはその実被害だけでなく、見た目にもグロテスクなので、可愛い観葉植物のルックスを損ねるという点でも本当に厄介な害虫です。白いふわふわとした埃のような:【コナカイガラムシ】
「コナカイガラムシ」は、殻を持たない、白いふわふわとしたロウ状の寄生虫です。 「オーガスタ」や「エバーフレッシュ」などといった、人気のある観葉植物に付く事でよく知られています。葉や枝の白い部分に手で触れてみて、ベタベタしてたら、コナカイガラムシに寄生されている可能性が高いみたいです。 一般的なカイガラムシ同様、コナカイガラムシも口から栄養を吸い取って、植物を枯らしたり、すす病になるリスクを高めます。 また、成虫後に葉に固着化する他の一般的なカイガラムシとは違い、コナカイガラムシは成虫後も体に足を持っているため、植木の中を自由に動き回る事が可能です。その為、葉の付け根などの狭いスペースに寄生する特徴があります。葉っぱに付いている:【コナジラミ】
「コナジラミ」は、セミのような2対の白い細長い羽をもつ、2mm程度の小さな害虫です。羽を有し飛ぶことが出来るので、行動範囲も広く、駆除してもすぐに近隣の畑やお庭などからやってきて植物に寄生するため、退治が困難な虫です。
カイガラムシ同様、口から針を出し、植物の養分を吸います。6月から10月といった、比較的、暖かい季節に繁殖するのも特徴のひとつです。
コナジラミの被害にあった葉は、緑の色素が抜け落ち、白いカスリ状に変化します。被害が進むと最終的には枯れてしまうので早めの対処が必要となります。厄介なのは、葉の裏側に住み着いていることが多いため、見つけにくく、気づいた時には被害が進行している恐れがあることです。また排泄物は、前述のすす病などを発生させる恐れもあります。植物をゆすって、白い粉が舞い立ったら、コナジラミの被害を疑ってみてください。
土の表面で飛ぶ:【トビムシ】
「トビムシ」は土の中に生息し、バクテリアや腐葉土を食べて生活している害虫です。そのため、土の入った鉢植えで生育する観葉植物は、トビムシにとっては絶好の温床となってしまうのです。 一般的にトビムシは、ジメジメとした湿度の高い環境を好むといわれ、その条件が揃えば大量発生する危険もあります。体長は2〜3mm程度、色は白、褐色、赤、緑とさまざまです。 トビムシというくらいですから、いかにも飛び上がりそうなイメージですが、実際は体に羽はありません。その代わり、腹部に飛ぶための器官を備えているため、外敵に接した際などには、10cm程度飛び上がる特徴があります。 植物を枯らすといった実害はないものの、土の中から這い出たトビムシが、植木鉢の中をピョンピョン跳ね回っていたらキモいですよね。大量発生しやすい:【ハダニ】
「ハダニ」は白い糸を出して葉に巣をつくるクモ科の害虫です。梅雨明け〜秋ごろにかけての、湿度が低く、暑い時期に繁殖します。 カイガラムシ等と同様に、口から針を出し、植物の養分を吸います。被害にあうと葉が黄色く変色し、徐々に全体に広がって落葉する場合も。 ただし、成虫後の体長が0.5mmと小さいため、肉眼では見つけにくいのが厄介です。ハダニを探す場合は、観葉植物を近くで観察し、葉の表だけではなく葉の裏も注意深く見るようにしてください。 なぜなら湿度に弱いハダニは、乾燥しがちな葉裏に集まる傾向があるからです。ハダニは強い繁殖力を持ち、メスは1日に5〜10個ぐらいの卵を産み、死ぬまでに100個ぐらいの卵を産みます。 そのため、大量発生しやすいので注意が必要です。またハダニは、その小さい体ゆえ、風によって運ばれてくるともいわれています。服やカバンなどにも付着しやすく、知らず知らずのうちに外から持ち込んでしまうことも。 あなた自身が害虫の運び屋だなんて最低ですよね。【虫の種類別】観葉植物に付いている白い虫の退治方法
ここでは、白い虫を退治する具体的な方法を虫の種類別にわけてご紹介します。市販の殺虫剤を使った退治方法に加え、工夫次第ではアナログな道具で白い虫を退治する事も可能です。ぜひ童心に立ち返った気持ちで読んでみて下さい。カイガラムシ
幼虫のカイガラムシは殺虫剤も有効なのですが、成虫したカイガラムシは、殻に覆われているため、殺虫剤が効かない事があります。 そんな時はちょっと面倒ですが、アナログな方法で退治していきましょう。 おうちにある歯ブラシを使って、カイガラムシをこそぎ落とします。取り除いたカイガラムシはティッシュに包んで燃えるゴミに出して大丈夫です。 また、目視できないカイガラムシが微量に残っている場合もあります。そんな時は、シャワーやホースを使って、葉の表面を水洗いしてください。 カイガラムシが葉の一部に密生している場合は、葉そのものを剪定ばさみなどで切り落とすのも有効です。成虫したカイガラムシ用の、浸透度の強い殺虫剤も市販されているので、そちらも併用してください。コナカイガラムシ
殻に覆われていない、「コナカイガラムシ」には、殺虫剤の効果が期待できます。 殺虫剤には、葉に直接散布するスプレータイプと、観葉植物の土に混ぜて使う浸透タイプの2種類があります。 スプレータイプは即効性があり、吹き付けると直ぐに駆除できるので便利です。観葉植物全体に被害が広がった場合は、浸透タイプがオススメです。土の中に混ぜてお水やりと一緒に撒きます。葉や枝の隅々まで薬がゆきわたるので、コナカイガラムシが拡散した際には有効です。コナジラミ
「コナジラミ」にはスプレータイプの殺虫剤が有効ですが、卵やサナギの段階では効果が期待できません。少し時間を置いて、幼虫〜成虫になった段階で、繰り返し殺虫剤を散布して下さい。 また、天然素材を使った退治方法もあります。牛乳と水を1:1で割った液体を観葉植物に散布する方法です。 100均などのスプレーボトルにこの液体を入れて散布して下さい。ただし、この方法も卵やサナギの段階では効果が期待出来ないので、コナジラミがある程度成長した段階で試してみてください。 コナジラミの黄色い場所に集まるという習性を利用した退治方法もあります。観葉植物の周りに黄色い粘着物を置き、そこに誘導して張り付かせる方法です。市販の既製品もありますし、黄色い画用紙や両面テープなどを使った手作りキッドでも対処可能です。トビムシ
「トビムシ」は殺虫剤の成分に弱いため、スプレータイプの殺虫剤が有効です。 飛びまわるトビムシを目視して、そのまま殺虫剤を散布させることで退治できます。目視できない場合でも、土の上に殺虫剤を撒くことで、トビムシの大量発生を予防する効果があります。ハダニ
「ハダニ」は水に弱い特性があるため、水の霧吹きを散布することで簡単に退治、繁殖の予防ができます。それでも退治しきれない場合は、スプレータイプの殺虫剤を散布して下さい。白い虫を退治する時に重要なポイント
白い虫退治の方法論として全般的にいえる事ですが、植物の状態を小まめに観察することが、虫の早期発見、早期駆除につながります。お水やりの際にでも、今まで気にしていなかった細かい部分を観察してみて下さい。きっと何か新しい発見があるはずです。葉の裏にも付いている可能性がある
目視しにくい葉の裏側は、害虫の溜まり場になっているかもしれません。 「コナカイガラムシ」、「コナジラミ」、「ハダニ」は、特に葉裏に付着しやすい害虫です。葉の表面だけでなく、葉の裏にも注意を払って生育するようにしましょう。殺虫剤で効果がないときは土の中に虫が潜んでいるので【植え替え】をしよう
殺虫剤が効かない場合、植え替えをしてみるのも良いかもしれません。なぜなら湿度が溜まってしまった古い土は、害虫の温床になってしまうからです。 新しい清潔な土に植え替えることで、害虫の寄生を予防する効果も期待出来ます。毎日、観葉植物を観察することが大切
大切な観葉植物を害虫から守るためには、毎日の観察が大事です。 葉の付け根や葉裏などは、害虫を見つけにくい場所なので、ズボラにしてると害虫の繁殖を見逃しがちです。 特にカイガラムシは、成虫後の退治が難しいため、幼虫の段階で早めに退治することが大事となってきます。 害虫の繁殖や被害が進まないよう、早期発見をするためにも、毎日の小まめな観察を心がけるようにしましょう。観葉植物に付いた白い虫の駆除おすすめ商品
虫の駆除に効くおすすめの商品を紹介します。キンチョール
昔からどこのお宅でも見かける殺虫剤の定番商品です。多くの害虫に対応している万能剤。もちろん、白い虫にも効果バツグンです。即効性に優れた製品ですが、土に散布することで害虫の予防対策にもなります。威力が強力な分、植物にも相応のダメージを与えますので、使用頻度はほどほどでお願いします。| 商品名 | キンチョール ハエ・蚊殺虫剤スプレー 450mL |
|---|---|
| 価格 | ¥497〜 |
| 有効成分 | ピレスロイド(d-T80-フタルスリン、d-T80-レスメトリン) |
| 対象 | ハエ成虫、蚊成虫、ゴキブリ、ノミ、トコジラミ、イエダニ、マダニ、コナカイガラムシ、トビムシ、コバエ |
| 特徴 | 微量でも即効性があり、害虫をすぐに退治することが出来ます。 |
アースガーデン やさお酢
100%食品成分で作られた製品です。その為、人体やペットへの健康被害の恐れはありません。害虫の発生の初期段階の駆除や発生以前の予防で効果を期待できます。お酢の力で植物を元気する効果も。デメリットは酢の匂いが気になる事ぐらいでしょう。| 商品名 | アースガーデン 食酢100%殺虫殺菌剤 やさお酢 1000ml |
|---|---|
| 価格 | 759円〜 |
| 有効成分 | 酢酸 |
| 特徴 | お酢100%の食品成分のため、あらゆる害虫の予防に使用でき、薬剤の弊害が気になる方でも安心して使用できます。 |
オルトランDX粒剤
観葉植物の土にまいて使っていただく製品です。浸透移行性の殺虫成分を2種類配合しているため、土から植物全体に殺菌効果が浸透していきます。直接の殺虫というよりかは、害虫予防の効果を期待できる殺虫剤です。キンチョールなどのスプレータイプの殺虫剤との併用がオススメです。| 商品名 | 住友化学園芸 殺虫剤 オルトランDX粒剤 200g |
|---|---|
| 価格 | 865円〜 |
| 有効成分 | アセフェート、クロチアニジン |
| 対象 | アブラムシ、コナカイガラムシ、コナジラミなど |
| 特徴 | 土にまくだけで植物に吸収され、植物全体を害虫から守る予防効果が長く持続します。 |
ベニカXファインスプレー
観葉植物の害虫と病気、両面をカバーする殺虫殺菌剤です。即効性と持続力にも優れ、アブラムシには約1ヶ月効果が持続するとのデータがあります。持続力が強いという事は、それだけ薬剤の成分が濃いという事でもあるので、過度な頻度の使用には注意しましょう。| 商品名 |
住友化学園芸 殺虫殺菌剤 ベニカXファインスプレー 1000ml |
|---|---|
| 価格 | 973円〜 |
| 有効成分 | クロチアニジン・フェンプロパトリン・メパニピリム |
| 対象 |
アブラムシ、カイガラムシ(幼虫)、コナジラミ、ハダニ、うどんこ病、黒星病など |
| 特徴 | 防虫と防菌、即効性と持続性の両立を実現。害虫の予防対策にも最適です。 |
観葉植物に白い虫が付かないようにする予防策
ここでは、白い虫が観葉植物に寄生してしまう前の段階で予防する方法を見ていきましょう。葉や幹だけでなく、土の状態のケアに気を配ることの重要性について示唆します。土の植え替えをする
土の植え替えをすることで、観葉植物の土の中にいる害虫や害虫の卵を駆除することが出来ます。 多湿環境を好む「トビムシ」の大量発生を防ぐためにも、湿度が適切な新鮮な土に植え替えることは大事です。また、あらかじめ防虫処理が施された土も市販されているので、植え替えの際に試してみるのも良いでしょう。土の上に化粧石をすると、虫からも乾燥からも防げる
観葉植物の生育に最適である、適温・湿潤な環境は、害虫の寄ってきやすい環境ともいえます。そういった弊害を「化粧石」で解消できるケースがあります。 清潔感やおしゃれな雰囲気を醸す目的で使われることの多い、「化粧石」ですが、虫が好む土を隠したり、根本に卵を植え付けられるリスクを軽減することも出来るのです。また「化粧石」は、土に蓋をし水分の蒸発を抑制することで、過度な乾燥から観葉植物を守ってもくれます。定期的に植木鉢を交換する
鉢を変えるタイミングとして、「根詰まり」というものがあります。鉢の中で根が生長しすぎて、水や養分を吸収しづらくなっている事です。鉢の底から根の先端が出ていたら、根詰まりのサインです。 植え替えをして、ひとまわり大きな鉢に移し変えてあげることで根詰まりは改善します。根詰まりが改善されることで、観葉植物は元気を取り戻し、害虫にも寄生されづらくなります。風通しの良い場所に観葉植物を置く
玄関・リビング・ベランダなど、風通しの良い場所に観葉植物を置くことで、成長促進、根崩れの防止、カビの発生の防止につながります。 どうしても室内の風の抜けが悪いようでしたら、サーキュレーターの設置を検討してみても良いかもしれません。枯れ葉やほこり発見するとすぐに取り除く
枯れ葉やほこりは害虫のえさになります。葉っぱの上のほこりやゴミは、濡れ雑巾などで小まめに拭き取り、鉢、受け皿の枯れ葉は、溜まる前に取り除く癖をつけましょう。観葉植物に虫がわかない生育方法は【ハイドロカルチャー】
実は、虫がよらない観葉植物の育てる方法があります。ハイドロカルチャーは水耕栽培なので虫がわかない
ハイドロカルチャーとは、土の代わりにハイドロボールという人工土を使って観葉植物を育てる方法です。ハイドロボールは微生物が存在せず、無菌で清潔ですので、ほとんど虫が寄ってきません。ハイドロカルチャーの観葉植物は世話も簡単
ハイドロボールは植木の鉢皿が不要なため、鉢皿から漏れた水で部屋が汚れることがありません。また、ハイドロボールは劣化することがないので、水洗いをして何度でも再利用することが出来ます。
穴のある鉢を購入する必要もないので、容器の選択肢が広がります。水やりも簡単で、水位計を使えば観葉植物の適切な水分状態を管理できます。適切な肥料管理と水管理ができるため、育ちすぎないメリットがあります。
このように、「ハイドロカルチャー」は観葉植物の登竜門としても最適な生育方法です。ハイドロカルチャーのおすすめの観葉植物
ハイドロカルチャーのおすすめの観葉植物を紹介します。パキラ
熱帯が原産の日当たりが良い場所に生育するパキラですが、お家で育てる観葉植物としてのパキラは、寒さ、暑さ、乾燥にも強く、多少日当たりの悪い場所でも元気に育つので、お部屋の環境を選ばない特徴があります。見た目も、コンパクトな根株の太いもの、大型の幹にねじりがあるものなど様々です。パキラの根は大きく張らず成育のスピードが速いため、一般的に生育に時間がかかるといわれているハイドロカルチャーでも、比較的短時間での生育が可能です。
| 商品名 | パキラ |
|---|---|
| 価格 | 330円〜 |
| 置き場所 | あるゆる場所に対応できる強さがあります。 |
| 花言葉 | 「勝利」、「快活」 |
| 特徴 | サイズ、価格、生育の難易度などの観点で初心者向きです。 |
サンスベリア
サンスベリアは乾燥に強く、耐陰性や耐寒性にも優れているので、初心者の方でも育てやすい観葉植物です。水やりの回数も少なくてすむので、根腐れの心配があるハイドロカルチャーにも適しています。ハウスダストを吸着し分解する効果もあるので、お部屋の空気が綺麗になるエコプラントとしても大変人気です!!
| 商品名 | サンスベリア |
|---|---|
| 価格 | 330円〜 |
| 置き場所 | 直射日光が当たらないカーテン越しの窓辺が理想 |
| 花言葉 | 「永久」「不滅」 |
| 特徴 | 空気を綺麗に保つエコプラント |
テーブルヤシ
「テーブルヤシ」はその名の通り、テーブルサイズのヤシ科の植物です。暑さ、多湿にも強く、耐陰性にも優れていますが、乾燥を嫌うため、エアコンの風が直接あたる場所は避けて飾ると良いでしょう。小ぶりで可愛いテーブルヤシですので、ハイドロカルチャーにして、お気に入りのグラスや瓶などで育てると、グッと映える印象になるでしょう。| 商品名 | テーブルヤシ |
|---|---|
| 価格 | 330円〜 |
| 置き場所 | 直射日光が当たらないカーテン越しの窓辺。エアコンの下は避ける |
| 花言葉 | 「あなたを見守る」 |
| 特徴 | テーブルサイズで可愛いです。 |
Q&A
ここでは、実際に起きるケースを想定して、Q&A形式でみなさまの疑問にお答えしたいと思います。白い虫の発生には必ず原因があり、その原因を取り除くことで、快適なボタニカルライフを送れるようになります!!Q,観葉植物に白くて小さいうねうねの虫が付いています。なんの虫ですか?
A,白い虫という事だけではハッキリと分かりませんが、葉の部分に寄生しているのであれば、「コナカイガラムシ」や「コナジラミ」が疑われますし、土の中であれば「トビムシ」かもしれません。うねうねしているという表現からもトビムシの可能性が疑われます。Q,エバーフレッシュは虫がつきにくいと聞きました。これは本当ですか?
A,率直に言いますが、嘘です。エバーフレッシュもカイガラムシ、ハダニなどの害虫の被害にあうことがあります。風通しの悪い場所で繁殖しやすいので、サーキュレーターを使って、空気の通りをよくする事で予防できます。Q,葉に沢山の虫がついて駆除しきれないのですが、葉を切り落としても大丈夫ですか?切ると枯れてしまわないでしょうか?
A,積極的に剪定することをオススメします。剪定をすることで、風通しをよくし、害虫の繁殖を予防する効果が期待できます。切ることで枯れることもありません。むしろ、古くなって疲れた葉を切り落とすことで、新芽に栄養がゆきわたり易くなります。白い虫から観葉植物を守れ!観葉植物に付いている白い虫の対策と予防策のまとめ
ここまで、観葉植物に寄生する白い虫の種類や特徴、その対策についてご紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか?
虫の種類や特徴、または育てる植物の種類によって、自ずと対応が変わってくることに気づいてもらえたかと思います。
まとめると、
- 観葉植物に寄生する白い虫には様々な種類、生態の違いがある。
- 虫の排便は、すす病などの二次災害を引き起こす可能性がある。
- 害虫を退治するには、それぞれの虫にふさわしい殺虫剤、防虫剤、道具(殺虫剤が効かない虫対策)を用意し、適切な方法で退治する必要がある。
- 観葉植物の植え替えや小まめな観察など、愛情を持ってお世話をすることが害虫の発見、予防にもつながる。
- ハイドロカルチャーは手軽に観葉植物を育てる方法であるとともに、害虫の発生するリスクを最小限におさえる生育方法でもある。
以上の5点をご紹介してきました。
害虫対策というと、何か大変なことのように思われるかもしれませんが、なにも気難しく考える必要はないと思います。なぜならば、観葉植物を害虫から守る上で一番大切なことは、その植物を可愛がることだからです。
小まめな観察を心がけることで、害虫を早めに見つけることもできますし、植物の健康状態の把握にもつながります。どうか、あなたの観葉植物がすくすくと育ち、あなたの生活の良きパートナーとなってくれますように。
最後までお読みいただきありがとうございました。