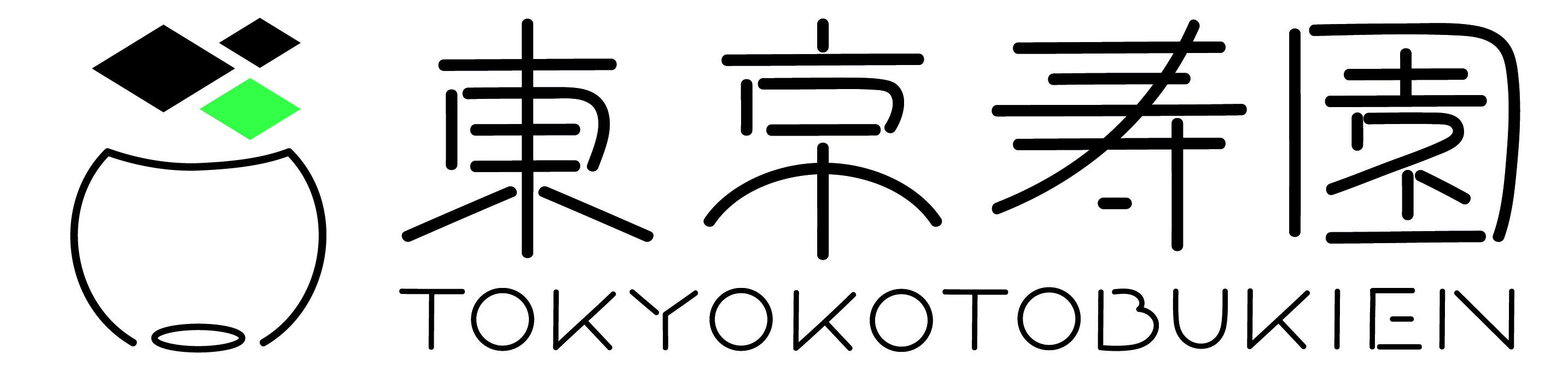目次
皆さんはガジュマルという植物を知っていますか?
ガジュマルは、沖縄地方では精霊が宿る常緑高木として親しまれており、「キジムナー」と呼ばれ、スピリチュアルな意味でもよく知られています。
熱帯から亜熱帯地方で見られる観葉植物のため、冬の寒さにはめっきり弱く、ケアをしてあげることがとても大切になります。
そこで、この記事では、
- ガジュマルが枯れる寸前の救済措置の方法
- ガジュマルが弱っているときのサイン
- ガジュマルが枯れる原因
- ガジュマルが枯れる前の対策
ガジュマルが枯れる寸前!救済措置はあるの?
ガジュマルが枯れてきたら、ひとまず枯れた部分を剪定します。 新芽が出てくる部分を除き、全体的に短めにカットし、小さめの鉢に植え替え、土を併せて入れてあげることをオススメします。 ガジュマルは、思い切って丸坊主にしても、また新たな新芽が出てくるので、安心してカットしてしまってください。大切に育てていたガジュマルが枯れてしまいそうになっている状況はたまに発生します
ガジュマルが枯れてしまうことを防ぐには、早期発見がとても大切です。 そして、枯れてしまいかけている原因を理解し、最適な方法で対処することで、復活させらえる可能性は十分にあります。あきらめないで!まだ復活する可能性は十分にあります
ガジュマルが枯れかけてしまう原因として考えられることは、「根腐れ」と「日照不足」の2点が考えられます。 十分に日光を浴びているにも関わらず、葉がシナシナになっている場合は、根枯れの可能性が高く、日陰で管理している場合は、日照不足が影響している可能性が高いです。 ただし、ガジュマルは直射日光が好きだからといって、日照不足の環境から急激に直射日光を当てることは、ガジュマルにストレスがかかってしまうため、行ってはいけません。 では、枯れる寸前のガジュマルは、どのようにして救い出せばいいのでしょう?今回は、枯れる寸前のガジュマルを救い出す方法についてお話しします
ガジュマルに「葉っぱが落ちる」という現象が現れたら、枯れる前のサインなので、見逃さないようにすることが大切です。 葉の様子を観察することで、ガジュマルに起こっているトラブルを知ることができ、その後の対処方法の一助になります。 では、実際にガジュマルが弱っているときのサインにはどのようなものがあるのでしょう?ガジュマルが弱っている時のサイン
上記でもご紹介したように、ガジュマルが弱っている場合、「葉を落とす」というサインをまず初めに出します。 おおまかなサインとして、以下の6点が挙げられるので、少し詳しくご紹介していきたいと思います。ガジュマルの枯れる寸前や異常をきたしているサインは「葉」に注目
ガジュマルのみならず、どの植物も往々にして葉にまず弱ってきているというサインが現れます。 毎日、葉の様子を観察することで、完全に弱ってしまう前に早期対応をすることが可能なので、枯れてしまうまで放置せずに済みます。葉っぱが枯れる
葉に元気がない様子が見られたら、先ほどからも何回もご紹介しているように、「根腐れ」もしくは「日照不足」を起こしているというサインです。 では、葉っぱの状態ごとにどのようなことが考えられるのか見ていきましょう。葉っぱにへたりが見られる
ガジュマルの下葉が垂れさがる状態になっている場合は、水不足が考えられます。 鉢を持ち上げてみて、軽くなっていないか、土が乾ききっていないかのチェックをしてみてください。 もし水分不足の場合は、鉢の底から水がたっぷり出てくるくらい水を注いで、ひとまず様子を見ることをオススメします。 土が湿っている場合は、根腐れ気味になっているということが考えらえるので、土をしっかり乾燥させ、できるだけ風通しの良い、直射日光が当たらないところで様子を見るようにしてください。 また、根詰まりを起こしている場合も、葉が下を向く様子を見せることも多く、水分や養分を上手く吸い上げられないため、このような症状になっていることがあります。 2年以上植え替えていない場合によく起こる現象で、鉢の底の部分から根が外に出ていたり、根が鉢の中で一杯になっていて、なかなか株が取り出せないなどの様子が見られると、この理由が考えられます。 早急に大きめの鉢に植え替える必要があります。 ちなみに、2年に1度、ガジュマルが元気な状態の時に植え替える最適な時期は、春秋の気温が高くなる時期です。葉っぱが落ちる
土が乾ききっていたり、反対に土に水分が多く含まれていて、根腐れを起こしかけている場合も、葉っぱが落ちるという症状に現れます。 また、気温が低く、5度を下回っている場合も、葉を落としやすくなるため、冬場は特に冷えを防いで、最低でも10度は確保できる室内がおすすめです。 ガジュマルにとって最適な環境で育ててあげるようにしてください。葉っぱが萎びてしまっている
葉が萎びてしまっている場合は、生育環境に原因があると考えられます。 観葉植物にもそれぞれの好みがあり、適切な環境で整えることで様々なトラブルを回避し、ガジュマルが枯れることなく、少し弱っただけで、すぐに復活させることが可能です。 ガジュマルを育てる上で気を付けなければいけない要点として、「水」「根詰まり」「葉焼け」「風通し」「肥料」が挙げられます。葉っぱがベタベタしている
夏場に多く見らえる現象で、これはカイガラムシやアブラムシが葉に発生することで起こります。 カイガラムシの成虫は、名前の通り、体を硬い殻で覆われており、薬剤での駆除が非常に困難なため、ピンセットで一匹ずつ取り除いたり、数が多い場合は、歯ブラシなどで擦り落としたりして駆除する必要があります。 カイガラムシやアブラムシは、ベタベタとした液を出すため、葉がベタベタとし、そのままにしておくと「スス病」を発生してしまうため、早急に対処する必要があります。 今では、カイガラムシ効果のある農薬も販売されているので、試してみてくださいね。葉っぱの色が変色している
ガジュマルを育てていると、葉の色が緑色から元気がなくなり、黄色や茶色、黒色に変色してしまう場合もよくあります。茶色
日光不足で葉が茶色になっている場合は、日光が当たる場所に移動させる必要がありますが、急激に環境を変えてしまうとガジュマルの負担になってしまうため、直射日光が当たらない場所や明るい窓際に置き換えるようにして、様子を見てください。 先ほども少し触れましたが、ガジュマルが耐えらえる最低気温は5度のため、できたら10度以上はある場所で、寒い時期を越せるようにしてあげることをオススメします。黄色
一番考えられる原因は、水不足か寒さ、肥料の与えすぎ、根腐れ、乾燥、虫によるもの、葉焼けです。 寒い時期以外の水分不足の場合は、土が湿る程度の水やりをこまめにするようにしてみてください。 根本近くの下葉が数枚、黄色くなっている場合は、主に新陳代謝の不良が考えられますが、他の葉が艶のある緑の色をしているなら、特に大きな問題ではないため、土の表面を清潔に保つことを心掛けてください。 新芽や新しく出てきた葉が黄色くなったり変形している場合は、「根詰まり」が考えられますので、大きめの鉢に植え替えることをオススメします。黒
ガジュマルの葉が茶色になっただけでも驚くのに、黒色になったら、ビックリするどころではないですよね。 これは、葉焼けで起こる現象で、夏場の直射日光を長時間受けていたり、普段日陰で過ごしているガジュマルを急に直射日光に触れさせたりすると起こります。 これは、早急に半日陰の場所にガジュマルを移動させてあげることで、進行を止めることができます。 ところが、ガジュマルの体力が大幅に弱ってしまっている可能性が高いため、注意を払いながら慎重に対処する必要があります。葉っぱに斑点がある
ガジュマルの葉に、斑点が出てきたら、一体何が起こったんだろうと、心配になってしまいますよね。 葉に見られる色によって、どのような原因が考えられるのか、順にご紹介していきます。黒い斑点
葉に黒い斑点が見られる場合は、「黒星病」または「葉焼け」が原因である場合が多いため、早急に適切な対応をする必要があります。 特に「黒星病」は、高温多湿な環境にガジュマルを置いている場合に多く発生する症状で、薬での対処の他、症状が見られる葉を切り落としてしまったのち、植え替えることで対処することができます。白い斑点
白い斑点が葉に見られる場合は、害虫が付着して起こっていることが多く、白い点や霞んだような跡がある場合は「ハダニ」が考えられますし、白い点のみの場合は「カイガラムシ」が原因であると考えられます。 「ハダニ」が原因の場合は、害虫スプレーを撒くようにしてください。 また、「カイガラムシ」が原因の場合は、すでに葉がベタベタしているという部分で記載したように、ブラシなどでカイガラムシを除去した後、葉を水で優しく洗い、清潔に保つようにしてください。そもそもなんでガジュマルが枯れるの?原因は?
ガジュマルは力強さや生命力といったスピリチュアルなイメージを持つ樹で、花言葉は「健康」です。 精霊が宿ると言われているほどの神秘的な樹ですが、その分、繊細な一面を持ち合わせているため、ちょっとした不注意で枯れてしまいやすい植物です。 では、どのようなポイントに注意をすれば、枯らさずに済むのでしょう?比較的丈夫で育てやすいとされているガジュマル
ガジュマルは一般的に、日光と水の調整さえ上手くできたら、育てやすいと言われています。 ところが、購入する時点で病害虫に感染している場合は、後々ガジュマルが弱ってしまう原因になってしまうことが多々あるため、注意が必要です。 また、ガジュマルの特徴は、艶のある葉と幹なので、出来るだけ葉に元気があり、幹も形が良い個体を選ぶようにしてください。ガジュマルが枯れる原因1:気根が根腐れしてしまってる場合
ガジュマルの気根が根腐れを起こす場合は、まず土の中に隠れている根が腐った後、幹にまで進行していきます。 「水が地中に溜まっている」「根詰まり」「肥料の与えすぎ」「菌の繁殖」「幹が地中に埋まっている」という原因が考えられるため、早期に対処するようにしてください。 ガジュマルの根腐れが重度の場合は、植え替えるか、挿し木をする方法でしか、ガジュマルを復活させる方法はないため、気根部分まで腐敗が進む前の早期発見がとても大切です。ガジュマルが枯れる原因2:ガジュマルへ与えてる水分不足の場合
ガジュマルの葉は、水分不足になると、葉が下を向くという現象が見られます。 この症状が出たら、土の中の水分は全くなく、すっかり乾いた状態になっているため、水やりをしなければならないタイミングだというサインです。 この状況が続くと、ガジュマルはそのまま枯れてしまうことになるため、発見したらすぐに水を与えるようにしてください。ガジュマルが枯れる原因3:日光を当てる日照時間が足りていない場合
日光が足りていない場合も、ガジュマルの葉はシナッとし、元気がなくなります。 その様な場合は、直射日光を避け、柔らかな光が届く場所に移動させることが必要です。 急激に強い日光を浴びてしまうと、葉焼けを起こしてしまうため、ガジュマルにとっては有り難くない環境の変化になってしまいます。ガジュマルが枯れる原因4:逆に日照時間が多すぎな場合
直射日光が長時間当たる環境も、日光が好きなガジュマルにとっては相応しくない状況です。 葉が日焼けを起こし、黒くなり枯れ落ちてしまい、ガジュマル自体が弱ってしまう原因になります。ガジュマルが枯れる原因5:害虫が原因の場合
主に「ハダニ」がガジュマルを枯らす害虫です。 小さくて動き回っており、放置しておくとあっという間に大量に増えてしまいます。 夏頃に発生し、ガジュマルの葉から養分を吸い取り生きているため、葉が全て枯れ落ちてしまいます。 そうなってしまってからでは手遅れのため、早期発見がとても重要です。ガジュマルが枯れる原因6:病気になってしまっている場合
ガジュマルが病気にかかることはかなりレアなケースですが、「黒星病」にかかることがあります。 これは、葉の内側に黒っぽいシミができたような状態になることで、主にカビが原因で発生する病気です。 対処法としては、症状の見られる部分を剪定して取り除いた後、清潔な新しい土や鉢に植え替え、風通しを良くし、市販の防除スプレーを振り、様子を見ることをオススメします。ガジュマルが枯れる原因7:気根が根詰まりしてしまっている場合
ガジュマルの根が、植木鉢の底から数本、外に伸びてきている場合、鉢の中で根詰まりを起こしている可能性が高いです。 この場合は、早急な植え替えが必要で、今使っている植木鉢より一回り大きいタイプを選ぶのがベストですが、ガジュマルの気根の形はそれぞれ違うため、気根の形や大きさに合わせて鉢を選ぶようにしてください。 また、水を与えてもしみこんでいかない場合も、根詰まりを起こしているサインになるので、見逃さないことが大切です。ガジュマルが枯れる原因8:植え替え後や剪定後の処理が適切でなかった場合
ガジュマルの剪定を行うと、切り口からラテックスというゴムの材料となる白い樹液が出てきます。 切り口の樹液を奇麗にふき取り、「癒合剤」を塗布し、傷ついた切り口に雑菌が入らず、早めにふさがるように対処しておかないと、知らず知らずのうちにガジュマルに菌が入ってしまい、弱って枯れてしまう要因になってしまいます。 ちなみに、ラテックスを手で直接触れると、肌の弱い人はかぶれてしまう場合があるため、園芸用の手袋や軍手を使用して作業するようにしてください。ガジュマルが枯れる前にできる対策法
ここでは、ガジュマルが枯れる前にあらかじめ気を付けておきたいポイントについてお話していきます。 植木鉢は下に穴が開いているタイプの「穴なし鉢」は、ほぼ確実に根腐れを起こしてしまうため、避ける方が無難です。 また、程よく日光が当たる環境にガジュマルを置くように心がけてください。気根が根腐れしてしまってる場合
ガジュマルの気根が根腐れを起こしている場合、これ以上症状を悪化させないためには、どのような対策が効果的なのでしょう?断水を行う
ガジュマルの根が腐ってきていると感じた場合は、一ヶ月ほど断水し、しっかり乾燥させることが大切です。 しばらく水立ちをしてガジュマルの様子を見るようにしてください。植え替え
ガジュマルが根腐れを起こした場合、鉢の中が根で一杯になる「根詰まり」を起こしていることが多く、根詰まりしたまま放置してしまうと、ガジュマル自身が水分をしっかり吸収することができず、どんどん弱っていき、挙句の果て枯れてしまいます。 オススメの植え替え時期は、遅くとも2~3年に一回、出来るなら毎年の植え替えがベストです。 また、植え替え後のケアも大切なポイントです。根腐れした気根のカット
根腐れを起こした気根をカットすることで、それ以上の悪化を防ぐことが可能です。 残しておきたい気根だけを残す方法や、すべて丸ごと剪定してしまう方法があります。 気根をカットしてしまう時のポイントは、出来る限り幹キリキリの部分を、思い切って剪定してしまうことです。ガジュマルへ与えてる水分不足の場合
水やりをするのにベストな時間は朝で、土が乾燥しているタイミングがオススメです。 植物の根は、地中で水分や栄養を吸収するのと同時に、呼吸も行っています。 ですから、土がいつも湿っている状態だと、根に酸素不足が起こり、呼吸困難で窒息状態になってしまいます。 ですが、必要以上に乾燥をさせてしまうことも、ガジュマルにとってはよくないため、水分がある状態と乾燥させている状態のメリハリをつけることが、とても大切です。水分をたっぷり与える
ガジュマルの土が水分不足で乾燥しきっている場合は、早急に水分をたっぷり与える必要があります。 上記でも記載したように、乾燥させる時はしっかり乾燥させ、水やりをするときはたっぷりと水を与えることが、ガジュマルを管理し、上手く成長させるためにはとても大切なポイントです。 では、ガジュマルをハイドロカルチャーで育てることは可能なのでしょうか?視覚的に管理しやすいハイドロカルチャーへの変更
ガジュマルは、意外にハイドロカルチャーとの相性が良く、メリットもたくさんあります。 [box04 title="メリット"]- 管理しやすく、清潔を保てる
- 虫が湧きにくい
- 水の量や根の様子が一目瞭然でわかる [/box04]
日照時間が足りていない場合・日照時間が多すぎてしてしまっている場合
日照時間が多すぎたり少なすぎたりするのも、ガジュマルの成長にとっては良くありません。 また、日光が好きなガジュマルだからといって、直射日光に長時間あてるのもよくありません。室内への移動
日照時間が長かったり、直射日光を長時間浴びる環境だと、葉焼けを起こし、枯れてしまいますので、半日陰の風通しの良い場所で育てるようにしてください。 また、寒さに弱いため、寒い時期には室内の日当たりがよく、あまり気温の変動が起こらない場所で成長させるようにしてください。 ただし、エアコンの風に直接あたると、急激に乾燥してしまうため、置く場所には注意が必要です。カーテン越しの日照への変更
夏場は、室内でも直射日光の当たる場所にガジュマルを置いている場合は、カーテン越しの程よい日当たりを心掛けるようにしてください。 春秋という季節は高温多湿を好むガジュマルにとっては、過ごしやすい時期ですが、日中ずっと直射日光に当たっているというのは、さすがに負担が大きく、弱りやすくなってしまうため、注意が必要です。害虫が原因の場合
ガジュマルに害虫が発生しているかどうかは、毎日のこまめな観察で防ぐ以外方法はありません。 ガジュマルが枯れる心配のないように、普段から日課として、様子を見るように心がけてください。ハダニの場合
ハダニは肉眼で見ると小さな赤い点に見え、風に乗って、葉が茂って風通しの悪いところをめがけて移動します。 そのため、風通しが良くなるように枝や葉を剪定したり、2.3日に1度の割合で、葉を水で一枚ずつ洗い流すという作業をすることで、ハダニを駆除することができます。カイガラムシの場合
日本で生息しているカイガラムシは、2種類ですが、世界的に見れば、7300種類いると言われています。 では、カイガラムシはどのようにして発生するのでしょう? [box02 title="発生要因"]- 知らないうちに人について移動
- 部屋が暗くほこりっぽい
- 風に乗ってやってくる
病気になってしまっている場合
既にガジュマルが病気にかかってしまっている場合は、早急に対策と手当てが必要です。活力剤を与える
ガジュマルの元気がないように思ったときは、「リキダス」や「メネデール」などの活力剤(栄養剤)を肥料と併せて与えてみることをオススメします。 手遅れになる前に対処をすることで、ガジュマルが枯れるのを防ぐことができます。諦める
どのような手を施しても、どんどん葉を落としてしまう場合や、腐敗が進んでしまう場合は、重度の症状なので、諦めるしか方法がない場合もあります。 挿し木を試みてみるのも良いですが、なかなか難しいため、一筋縄ではいきません。 手遅れになる前に、日々こまめなチェックを心掛け、ガジュマルを大きく育てたいですね。気根が根詰まりしてしまっている場合
ガジュマルの気根が根詰まりを起こしていて枯れる様子が見られるときは、早急に今使っている植木鉢より大きめの鉢に植え替える必要があります。 根詰まりを起こしているということは、ガジュマルの根に傷がついている可能性もありますし、この状態で栄養剤を入れてしまうと、良い効果を発揮するどころか、ガジュマルの負担にしかなりません。 そのため、新しい植木鉢で安定するまでは、植え替え後のケアがとても重要になってきます。 鉢の中で根っこが固く巻いてしまっている場合は、優しく「ほんの少し」ほぐしてあげることで、大き目の鉢に植え替えた後、地中に自分で根を広げて張るようになります。植え替え後や剪定後の処理が適切でなかった場合
ガジュマルにとって、植え替えはとても大きな負担です。 そのため、元気でピンピンしているガジュマルでも、植え替え後のケアを間違うと、一気に弱ってしまうなんていうことも、あり得ます。 植え替え後は、2週間ほど明るめの日陰に置き、水は溜まらないように気を付けながら、たっぷり与えるようにしてください。気温の極端な夏や冬にしてしまった場合に多い
ガジュマルを植え替えるのに適した時期は、すでにご紹介したように、春秋の暖かい時期です。 もし、夏や冬といった、気温が極端に変化する時期に植え替えをしてしまった場合は、ガジュマルに想像以上の負担がかかるため、枯れる可能性が高くなります。上記のシーズン以外であれば挿し木で新たにガジュマルを育てる
ガジュマルの挿し木に挑戦する場合は、「挿し木用の土」を必ず用意し、「発根促進剤」を枝の切り口に塗ることで、光合成する力が高まり、根がスムーズに生えてきやすくなります。下葉が落ちてしまっている場合は葉水をしっかりと与える
ガジュマルの下葉が落ちる現象は、葉の水分が不足していたり、乾燥してる場合や、葉に害虫が付いている場合などが考えられるため、葉に水をしっかり含ませることで、もう一度元気を取り戻すことが可能です。 普段から霧吹きを使って葉水を行うことで、害虫であるハダニやアブラムシなどを落とすことができますし、なんといっても害虫が好きなホコリを除くことができます。ガジュマルが枯れるのはスピリチュアル的にもあまり良くないこと
植物にとって「枯れる」という現象は、「死」を意味します。 幸せを呼ぶ木として厄除け効果が高く、精霊が住み着くと言われているガジュマルが枯れるなんて、一大事ですよね。ガジュマルは風水の中では厄除けや幸せを呼ぶ効果などがある観葉植物とされている
風水では、ガジュマルは眺めている人の気分を落ち着かせたり、リラックスさせたりする効果があると言われています。 ガジュマルは、「陽」の気を持つ観葉植物なので、リビングや寝室・キッチンなどに置くと良いとされています。植物が枯れるというのは代理で悪運を受けてくれたという考えもある
大切に育てている植物が枯れるのは、とても悲しい気持ちになりますよね。 ですが、実は「枯れる」という現象で、その植物自身のことを可愛がって育ててくれた人を、悪運から守っているとも言われます。適切に育てていい気をしっかりと取り込もう
とても神聖でパワーのあるガジュマルですから、出来ることなら大切に育てて、良い気を引き寄せてきて欲しいと思いますよね。 そのためにも、ガジュマルに適した環境や成長のポイントを押さえ、順調に育てていきたいものです。ガジュマルを実生苗や種植えで育て始めた場合は枯れることはよくある
ガジュマルを種や苗から育てるのは難しいと言われています。 ごくまれに、5月頃になるとインターネットで種が販売されている場面に出くわすことがありますが、なかなか簡単には発芽するところまでたどり着かないのが現実のようです。素人が種からガジュマルを育てるのは非常に難しいとされている
ガジュマルを種から育てるには、土で種を埋めてしまわないのがポイントです。 発芽するためには、多くの光が必要なため、土をかぶせてしまうと日光不足で発芽できません。 そのため、水やりも慎重に行う必要があり、スプレーを使って行うと安心です。 発芽には25℃前後の気温が必要なため、適温での管理がとても重要になってきます。 この気温を確保しようと鉢にラップをかぶせたりして保温すると、蒸れすぎるなどの問題が発生してしまうこともあるため、慎重に行う必要があります。 このように、ガジュマルを種から発芽させるまで、様々な面で微調整が必要なため、なかなか素人では難しい点が多々あります。新芽が出たのに枯れてしまうなんてこともあるそう
ガジュマルの新芽が出て、喜んでいたのもつかの間、一日経過して枯れるなんていうことも、よくあるようです。 新芽はとても柔らかくデリケートなため、強い日差しに当たったり、逆に日照不足になったりしたら、すぐに弱って枯れることが多く、管理が難しい部分です。 大きくしっかりした幹が出来上がっている場合の新芽は、それほど気を遣わなくても大丈夫すが、種から発芽したての新芽は、かなりの注意が必要です。しかし、うまくいけば太く立派なガジュマルが育つので是非チャレンジしてみては?
種から発芽したガジュマルが大きく育っていくのは、毎日育てていて、とても嬉しいですよね。 まして、太く立派なガジュマルに育ってくれたら、なおのことです。 ぜひ、チャレンジ精神を持って、立派なガジュマルを育ててみてくださいね。ガジュマルが枯れる寸前はどうなる?枯れない対策を徹底解説のまとめ
この記事では、ガジュマルが枯れる場合に考えらえることについて、様々な方面から解説してきましが、いかがでしたか?- ガジュマルが枯れそうになっていた葉の様子を観察する
- ガジュマルの葉に見られる症状はいろいろある
- 日照時間が多くても少なくてもガジュマルには良い環境ではない
- 害虫や病気にかからないようにするには早期発見が大切
- 水やりのタイミングを間違わないように
- ガジュマルが枯れるのはスピリチュアル的にもよくない
- ガジュマルを種や発芽から育てるのは至難の業